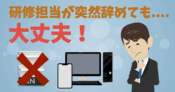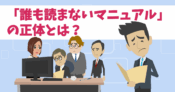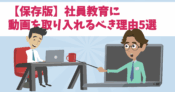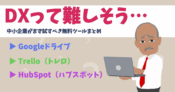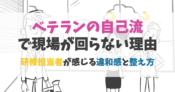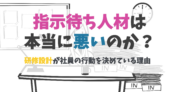社員が「研修を受けたふり」になる本当の理由~なぜ学びが“定着しない”のか? 企業が見落としがちな盲点~
「研修はやった。でも現場では何も変わらない」
「テストの点数は良いのに、実務では活かせてない」
そんな“学んだふり”現象、あなたの会社にもありませんか?
実はこれ、「社員のやる気がない」の一言では片づけられない、もっと深い“構造的な問題”があるんです。
第1章:そもそもなぜ「ふり」が起こるのか?
「受け身の研修」が作り出す“学んだ気”
- 講義形式で座って聞くだけ
- 眠気との戦いに耐える90分
- 最後にテストがあるから一応メモを取る
…はい、これ全部“受けたふり”の典型です。
インプットだけでアウトプットがないと、人の記憶には残りません。
つまり、定着しない。
“研修を消化する”ことが目的化していないか?
- 「今月中に新人研修終わらせておいてね」
- 「eラーニングの受講率は100%です!」
これはもはや受講がゴールになってる研修。
社員にとっては“クエスト完了”のようなもので、実務とのつながりは感じられていないケースが多いです。
第2章:「受けたふり」を加速させる3つの環境要因
① 上司が研修に無関心
研修から戻っても、上司から一言も触れられない。
「で?何か学んだ?」とすら聞かれない。
これでは、研修は“誰にも見られていない作業”と化します。
学びが職場で話題にならないと、社員は「重要じゃない」と判断する
② 業務と研修のつながりが見えない
「いつ使うのこれ?」
「現場のやり方と違うんだけど…」
こんな声が出るのは、研修の内容が“現場に降りてきていない”証拠。
実務でどう活かすかを考える設計がなければ、記憶からどんどん風化していきます。
③ アウトプットの機会がない
教わって終わり、になっていませんか?
- 実際にやってみる演習がない
- 成果物を上司に見せる仕組みがない
- 振り返りの場がない
こういった**“出す場”の欠如**が、記憶定着の邪魔をしています。
第3章:「ふり」を卒業するために企業ができること
チェックより“活用”に目を向ける
- 「受講しましたチェック」だけで終わらせない
- 「学んだことをどう活かす?」を必ず聞く
- 上司も同席 or フォローアップ面談を設ける
学びの“スモールゴール”をつくる
研修→1ヶ月以内に実践→上司に報告、のように、
行動とセットの目標設計を入れることで、自然と実践する流れが生まれます。
「説明する機会」が最大のアウトプット
「誰かに教える」は、記憶を強く定着させます。
OJTのなかに、「教わったことを説明させる」時間を組み込むのも効果的です。
第4章:「研修は意味がない」の誤解
「研修って、やっても変わらないよね」
という声。
実はこれは**“研修の設計に問題がある”**のであって、
研修そのものがムダなわけではありません。
✅伝えっぱなし
✅一方通行
✅現場と分断
これらを見直すことで、研修は“形だけ”から“行動を変えるもの”へと進化します。
第5章:「ふり」に気づく3つのサイン
- 研修を受けたはずなのに、業務手順が変わらない
- 「前と何が違う?」と聞いても答えられない
- 学んだ内容を他人に説明できない
この3つに当てはまったら、要注意。
学んだ“つもり”になってるだけかもしれません。
第6章:明日から変える、研修との向き合い方
●新人には「教える側」に立ってもらう
学びは、受けるより教える方が何倍も記憶に残ります。
ローテーションで「ミニ先生役」を作ってみましょう。
●学びの共有文化を作る
Slackでも社内報でもOK。
「こんなこと学びました」「ここに使えそうです」を
発信する仕組みがあるだけで、研修が“会社全体の資産”になります。
●動画で繰り返し学べる仕組みを
一度聞いても忘れてしまうのが人間です。
繰り返し学べる環境こそが、定着のカギ。
おわりに:研修は“きっかけ”。行動を変えるのは職場の仕組み
「ふり」で終わってしまう研修の背景には、受講者の姿勢だけでなく、企業側の設計や職場環境の課題があります。
だからこそ、研修を“やったら終わり”にするのではなく、研修を“起点”にして、職場でどう変化を起こすかまで設計する必要があります。
研修をきっかけに行動が変わるには、3つの視点が欠かせません。
1つ目は、「現場との接続」です。
研修の中で、実務との関係性をどれだけリアルに描けるか。これは参加者にとって、“自分ごと”として吸収できるかどうかに直結します。
2つ目は、「アウトプットの設計」です。
聞いて終わりではなく、実際に使ってみる機会をどう設計するか。
ここが不十分だと、学びは一瞬で風化します。演習、シェア、現場でのトライアルなど、小さくても“行動”を生み出す工夫が求められます。
3つ目は、「周囲の関与」です。
特に上司の関心や声かけは強力な効果を持ちます。
「あの研修どうだった?」
「実務で使えた?」
と聞かれるだけで、学びは“意味のあるもの”として再認識されます。
そして忘れてはならないのが、研修はあくまで“スタートライン”であるということ。
そこで得た知識や視点が、日々の業務や行動にどのように落とし込まれるか。
ここを支えるのは、結局のところ“現場の仕組み”であり、企業文化なのです。
- まずは、受講後の対話を増やす。
- 学びを共有する文化をつくる。
- そして、研修の設計を「実践ありき」に変えていく。
そんな一歩が、明日からの研修の価値を、ぐっと高めてくれるはずです。
答えは、意外とすぐ近くにあるかもしれません。
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
この研修の課題、テーマはアニメーション動画との相性抜群です。
視覚で伝える・ストーリーで理解させる・ナレーションで補完する、という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください。