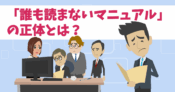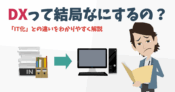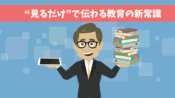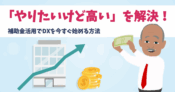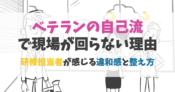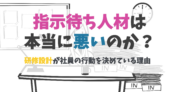研修担当が突然辞めても大丈夫!動画で“人に頼らない教育”を実現する方法
突然ですが、みなさんの会社では新人研修や業務の引き継ぎ、どんなふうに行っていますか?
- 「とりあえず先輩社員がつきっきりで教える」
- 「新人が来るたびに毎回説明する」
- 「研修資料? どこにあるか知らないなあ…」
そんな状況が当たり前になっている企業、実はかなり多いです。
でも、そのままで本当に大丈夫ですか?
特に問題になるのが、研修担当者が辞めたとき。
あの人じゃないと分からない――そんな仕事が残されていたら、正直キツいですよね。
この記事では、そんな悩みを解決する「教育動画」のメリットと活用法について、実例やノウハウをご紹介します!
第1章:研修担当が辞めると、なにが困るのか?
ノウハウが消える
退職する人が、社内教育の中心人物だった場合。
その人が持っていた知識や説明のコツ、資料の使い方などがごっそり消えることになります。
紙のマニュアルが残っていても、それだけでは不十分なことも。
結局、新しく担当を引き継いだ人がまた一から作り直す羽目になります。
教える内容が毎回変わる
「Aさんに教わったときと、Bさんに教わったときで説明が全然違う!」
なんてことありませんか?
属人化した研修は、教える人の力量や感覚によってバラつきが生まれます。
こうなると、新人が混乱してしまい、せっかくの教育が逆効果になることも。
教える側も疲弊している
毎回、毎回、同じ内容を説明する。
しかも「この説明、伝わってる?」と不安になりながら…。
正直、教える側のモチベーションも下がります。
さらに、本来の業務時間を削って新人教育に時間を取られると、既存社員のパフォーマンスも落ちてしまいます。
第2章:教育動画って、なにがそんなにすごいの?
一度作れば、ずーっと使える
教育動画の最大の魅力は「ストック型コンテンツ」であること。
一度しっかり作り込めば、それを何度でも・誰にでも使いまわせる。
何十人いても、何年経っても同じ品質で教育できるんです。
新入社員が来たら「まずはこの動画を見てね」でOK。
これだけで、研修の負担がグッと減ります。
教える人によるバラつきがゼロに
動画は「いつでも、どこでも、誰が見ても同じ内容」が流れます。
つまり、研修の“品質”がブレないんです。
誰が教えるかで伝わり方が変わる心配もなし。
これは実は、管理職や現場のリーダーからも非常に好評なポイントです。
何度でも見返せる=理解が深まる
人から説明を聞いたときって、「聞き逃したら終わり」ですよね。
でも動画なら、聞き逃してもOK。止めて、戻して、繰り返し視聴できます。
これが、新人や若手社員にとってめちゃくちゃ安心感があるんです。
自分のタイミングで学べるって、現代の教育においてかなり重要なポイントですよ。
第3章:実際に教育動画を導入した企業のリアルな声
ケース①:毎月10人以上が入社するIT企業
この会社では、研修担当が1人。
OJTでは物理的に手が回らなくなっていたそうです。
そこで、よくある質問や基本操作を動画にまとめたところ…
- 担当者の説明時間が月30時間以上削減
- 新人の立ち上がりスピードが平均2週間→5日に短縮
- 社内アンケートで「理解しやすい」「自信を持って業務に入れた」と高評価!
まさに、教育の効率と品質が同時にアップした事例です。
ケース②:全国チェーンの飲食店
この企業では、店舗ごとに教育スタイルがバラバラで、サービスの品質にもばらつきが。
「同じ会社なのに接客に違いがあるのはマズい」という危機感から、教育動画を本部で制作。
- 全店で共通の研修動画を導入
- アルバイトでも初出勤前に視聴→即現場投入が可能に
- 店長の「教育時間」が月10時間以上削減
全国規模でも“教育の統一”を実現できるのが、動画の強みです。
第4章:動画×マニュアル=最強の教育ツール!
「動画だけあればOK」と思いがちですが、
実は「紙 or PDFマニュアル」と組み合わせると、さらに効果がアップします。
理解 → 定着の2ステップ
- 動画:視覚と音声で直感的に理解
- マニュアル:あとで読み返して細かいところをチェック
この2段構えが、理解と定着のW効果を生みます。
特に新人社員は、最初は動画で全体像を掴んで、あとからマニュアルで確認するという流れが好まれます。
動画に「マニュアルリンク」を貼るのも◎
YouTubeや社内ポータルに動画をアップして、概要欄にマニュアルのリンクを貼ると便利。
双方向で補完できる設計をしておくと、「分からない…」と迷子になる社員が激減します。
第5章:どんな動画を用意すればいいの?
「教育動画って何を撮ればいいの?」とよく聞かれますが、
まずは以下のジャンルから始めるのがおすすめです。
よくある定番コンテンツ
- 会社紹介・理念動画:社長メッセージもあると◎
- ビジネスマナー:電話対応、名刺交換、メールの書き方
- 業務の流れ:各部署の基本的な仕事の流れを動画化
- 社内ツールの使い方:Slack、Googleドライブ、チャット、勤怠管理など
- トラブル対応マニュアル:クレーム対応、トラブル時の連絡ルートなど
こういった動画は一度作っておくと、部署異動や中途採用でも流用可能です。
第6章:動画教育は“辞める人”ではなく“残る人”のためにある
教育動画の本質は、単なる“研修の代替”ではありません。
むしろ、「残る人たちが働きやすくなる仕組み」を作るという意味で、未来への投資なんです。
教える側のストレスが激減
「またこの説明か…」というモヤモヤから解放されます。
説明に疲れて無意識に雑になっていた部分も、動画なら常に安定した品質で伝えられます。
新人の“早期離職”を防ぐ
新人が何も分からないまま放置されると、不安やストレスで離職の可能性が高まります。
動画で基礎をしっかり押さえることで、「ちゃんと育ててもらってる」感を得られ、定着率が向上します。
第7章:まず何から始める?5ステップでOK
ステップ①:「よく説明してること」を洗い出す
まずは、社員みんなに「最近新人に何をよく聞かれる?」と聞いてみましょう。
実は同じような質問が繰り返されていることに気づきます。
ステップ②:動画に向いてるものを選ぶ
手順があるもの、図解が必要なもの、口頭説明が多いものは動画向きです。
ステップ③:スマホやZoom録画などで試作
いきなり本格的なものを作る必要はありません。
まずは社内向けに、簡単なナレーション付きスライド動画でもOK。
ステップ④:社内でテスト → フィードバック
作った動画を新人に見てもらい、わかりにくい部分はないか確認。
フィードバックをもとに改善します。
ステップ⑤:定番コンテンツを量産!
効果が実感できたら、いよいよ本格的に動画教育の仕組みづくりへ。
この時点で外注を検討してもOKです。
第8章:まとめ 〜 教育を“人”から“仕組み”へ 〜
人材の流動性が高くなっている今、「教育は人がやるもの」という考え方には限界があります。
教育の仕組みを“資産化”することで、組織全体の生産性と安定性がグッと高まります。
そして、教育動画はその中核を担うツールです。
- 新人が迷わない
- 先輩社員の負担が減る
- 研修の品質が上がる
「教える人がいないから教えられない」ではなく、
「仕組みで教育がまわる」状態を、ぜひあなたの会社でも実現してください。
🔍 おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
この研修の課題、テーマはアニメーション動画との相性抜群です。
視覚で伝える・ストーリーで理解させる・ナレーションで補完する、という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください。