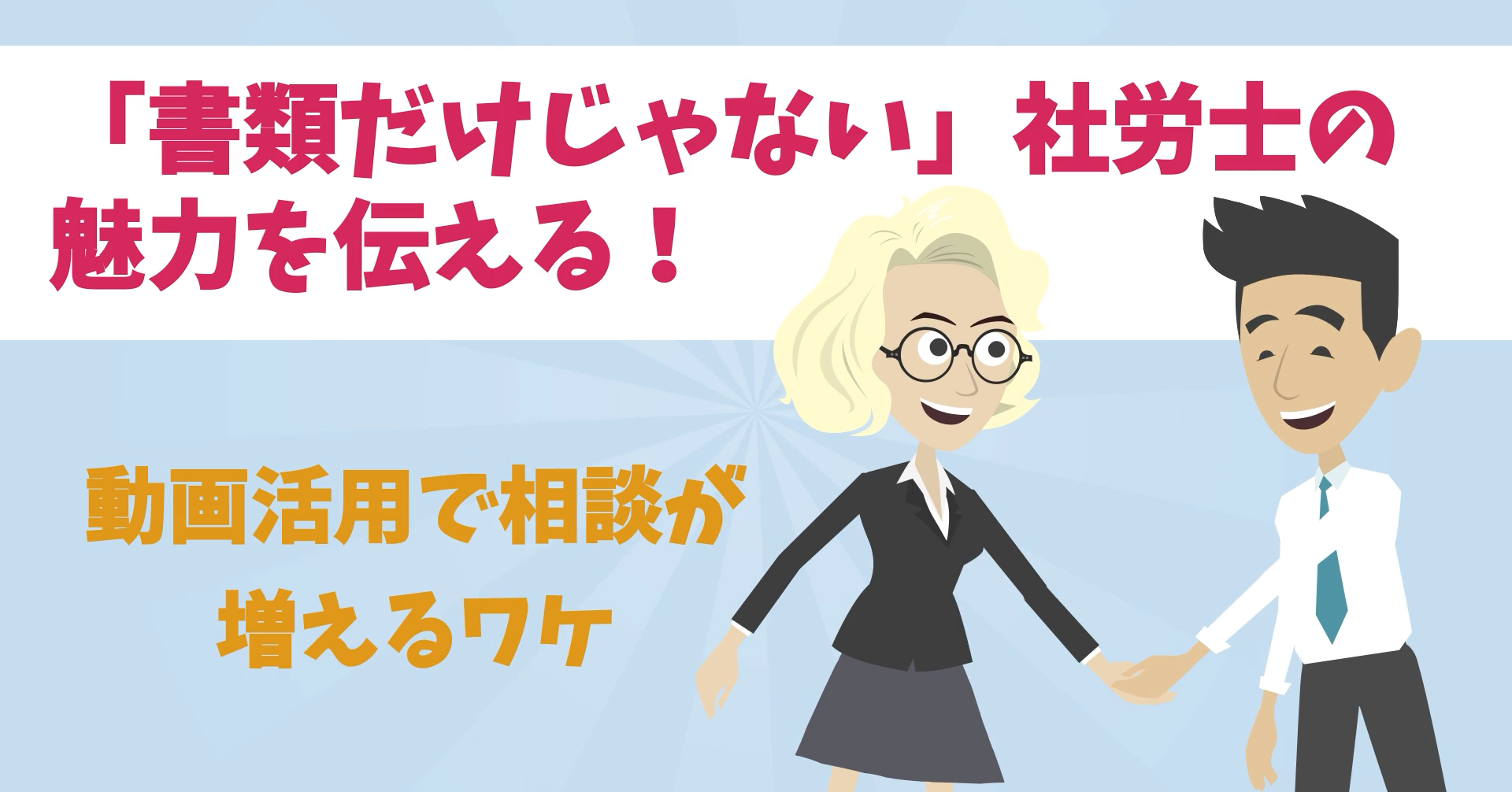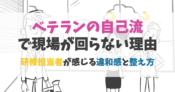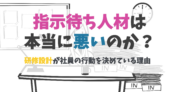「書類だけじゃない」社労士の魅力を伝える!動画活用で相談が増えるワケ
「社労士の仕事って、AIに奪われるんじゃない?」そんな不安を感じていませんか?
こんにちは!
もしあなたが社会保険労務士(社労士)として働いていて、こんな風に思ったことがあるなら…この記事はお役に立てると思います。
最近、書類作成や提出手続きの仕事が減ってきた気がする。
昔より、顧問先の相談が少なくなってきたかも。
もっと新しいお客さんに出会いたいけど、どうすればいいの?
そんなあなたにこそ、今の時代にぴったりな“伝え方”があります。
それが、「動画」という手段です。
でも安心してください。
この記事は「動画制作をしましょう!」と売り込む話ではありません。
あくまで、動画という手段を使うと、なぜ社労士としての魅力や専門性が“ちゃんと伝わる”のかをわかりやすくお話していきます。
社労士の仕事は、実は「見えにくい」
まずはここから!
社労士の業務って、大きく分けて以下の3つがありますよね?
- 書類作成(就業規則や各種申請書など)
- 行政への提出手続き代行
- 人事労務のコンサルティング業務
この中で、一番「伝わりやすい」のは、実は書類作成なんです。
なぜなら「見える」から。
でも問題はここから。
コンサルティングって、何をやっているのかが外から見えない。
成果もすぐには分かりにくい。
そうなんです。
たとえば、「働き方改革に対応したアドバイスをしました!」といっても、それを知らない人には価値が伝わらない。
だからこそ、動画という「見える化」が大きな力になるんです。
書類と手続きはAIの得意分野に。社労士の本領は「相談力」
時代の流れを見てみましょう。
いま、AIやRPA(業務自動化ツール)によって、書類作成や提出の自動化がどんどん進んでいます。
つまり——
「やらなくていい業務」はどんどんAIに任せられるようになっている。
これは悪いことではありません。
むしろ、社労士の仕事が“より人間的な領域”にシフトしている証拠です。
たとえばこんなテーマ、今どきの企業はすごく悩んでいます。
- テレワークの制度整備
- 育休後の職場復帰支援
- ハラスメント対策
- 外国人雇用の実務
これらは、正直「マニュアル」や「AI回答」では対応できません。
だからこそ、社労士という“相談できる存在”の価値が上がっているんです。
とはいえ…その「価値」、ちゃんと伝わってる?
ここが最大の課題です。
どんなに専門性があって、どんなに実績があっても——
それが伝わらなければ、存在しないのと同じ。
ホームページに「就業規則作成」「助成金申請支援」と書いても、
正直なところ、どの社労士さんも似たようなことを並べてますよね。
つまり、
「この人に相談してみよう!」と感じてもらうには、“言葉だけでは足りない”のです。
なぜ動画?3つの理由で「選ばれる社労士」へ
ここで、ようやく動画の話に入ります。
でも「動画にするのがゴール」じゃないんです。
目的はあくまで、「信頼してもらう」「相談してもらう」こと。
そのために、動画には以下のようなメリットがあります。
① 無形サービスを“見える”ようにできる
コンサル業務の内容って、普通の人からするととても抽象的です。
でも動画にすれば、
- 実際に相談を受けているシーン
- 企業がよく悩むポイントへの解説
- 成果事例(もちろん個人情報は配慮して)
などが“ストーリー”として伝えられます。
「この人、ちゃんと現場をわかってくれてる」
そんな風に感じてもらえたら、それはもう半分「信頼」を得たようなものです。
② 「相談しやすい人」に見える
社労士に限らず、士業の先生って「ちょっと堅そう…」と思われがちです。
でも動画では、声のトーン、話し方、表情など「人柄」が伝わります。
とくに、
- 自分の言葉でやさしく話している動画
- 顔出しで自己紹介している動画
こういったものは視聴者に安心感を与えて、「相談しようかな…」という気持ちにつながります。
③ 情報提供で“専門家ポジション”を確立
動画を定期的に発信すれば、「あの人は労務のことをいつも教えてくれる人」という印象が定着します。
SNSやYouTubeを活用すれば、専門家としての存在感も自然に育ちます。
SEO効果も狙えるので、検索でも見つけてもらいやすくなるのも◎。
どんな動画を作ればいいの?2つのターゲットを意識しよう
社労士が動画を活用するとき、大きく2つのターゲットがあります。
(1)企業の担当者(社長・人事・総務など)
→ 社労士に業務を依頼してくれる見込み客です。
この層には「役立つ情報」を届けましょう。
例:
- 「知らないと損する助成金まとめ」
- 「従業員からの相談対応の基本」
- 「就業規則のNGワード集」
- 「社長が知っておくべきハラスメント対策」
こういった情報を、ちょっと雑談を交えながら話すだけでもOKです。
「この人、話しやすそう」と思ってもらえれば、大成功。
(2)社労士を目指す受験者
→ 資格スクールや講座の紹介にもつながります。
この層には「試験対策」や「講座の紹介」などが効果的です。
例:
- 「労働基準法のよく出るポイント解説」
- 「過去問を解説するシリーズ動画」
- 「受験勉強のコツ&モチベ維持法」
資格の合格率が約6%と厳しいからこそ、勉強法に悩んでいる人は多い。
そんな人たちの“最初の伴走者”になれる動画は、スクールや教材の集客にもつながります。
動画を作るときのコツ3つ
作る前に知っておきたいことを3つだけ。
1.誰に見てもらいたいかを決める
ターゲットが変われば、内容も口調も構成も全部変わります。
なので、最初に「誰に向けた動画なのか」をはっきりさせましょう。
2.ゴール(目的)を決める
- 顧問契約を増やしたい?
- 単発相談を増やしたい?
- 講座を広めたい?
ゴールを明確にすれば、「どんな話をすればいいか」も見えてきます。
3.見る人に優しい編集を
難しく考えなくて大丈夫です。
- テロップを入れる
- 重要な話の前に「ポイントは…」と区切る
- 長すぎない(5〜10分程度)
これだけでも視聴者に伝わりやすくなります。
「映像がオシャレ」より「中身がわかりやすい」が正義です!
実際にある!社労士が出演している動画事例
● 社労士法人WORKidの「保険適用拡大」対策動画
改正予定の健康保険や年金制度について、社長がどう対応すればいいのかを解説。
「ちょうど困ってたんだよね」という企業担当者からの信頼につながります。
● パワハラ対策の動画
実際に相談を受けた経験をベースに「どう対応すべきか?」を話すスタイル。
リスク回避に関心のある企業には、こういう“リアルな知見”が刺さります。
【まとめ】社労士こそ「伝え方」で差がつく時代へ
社会保険労務士としての価値は、これからますます「相談できる存在」であるかどうかにかかっています。
その価値をどうやって伝えるか?
書面だけでは足りません。
会って話すのも大切ですが、もっと手前の段階で「この人に聞いてみたい」と思ってもらえるような“きっかけ”が必要です。
それが、動画です。
あなたの知識も経験も人柄も、ぜんぶまるごと伝わる方法が、ここにあります。
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
映像制作テンツキでは
- クライアント用説明動画
- 新人社員用マニュアルの動画化
- 研修動画
などアニメーション動画の制作をさせていただいております。
- 視覚で伝える
- ストーリーで理解させる
- ナレーションで補完する
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください!