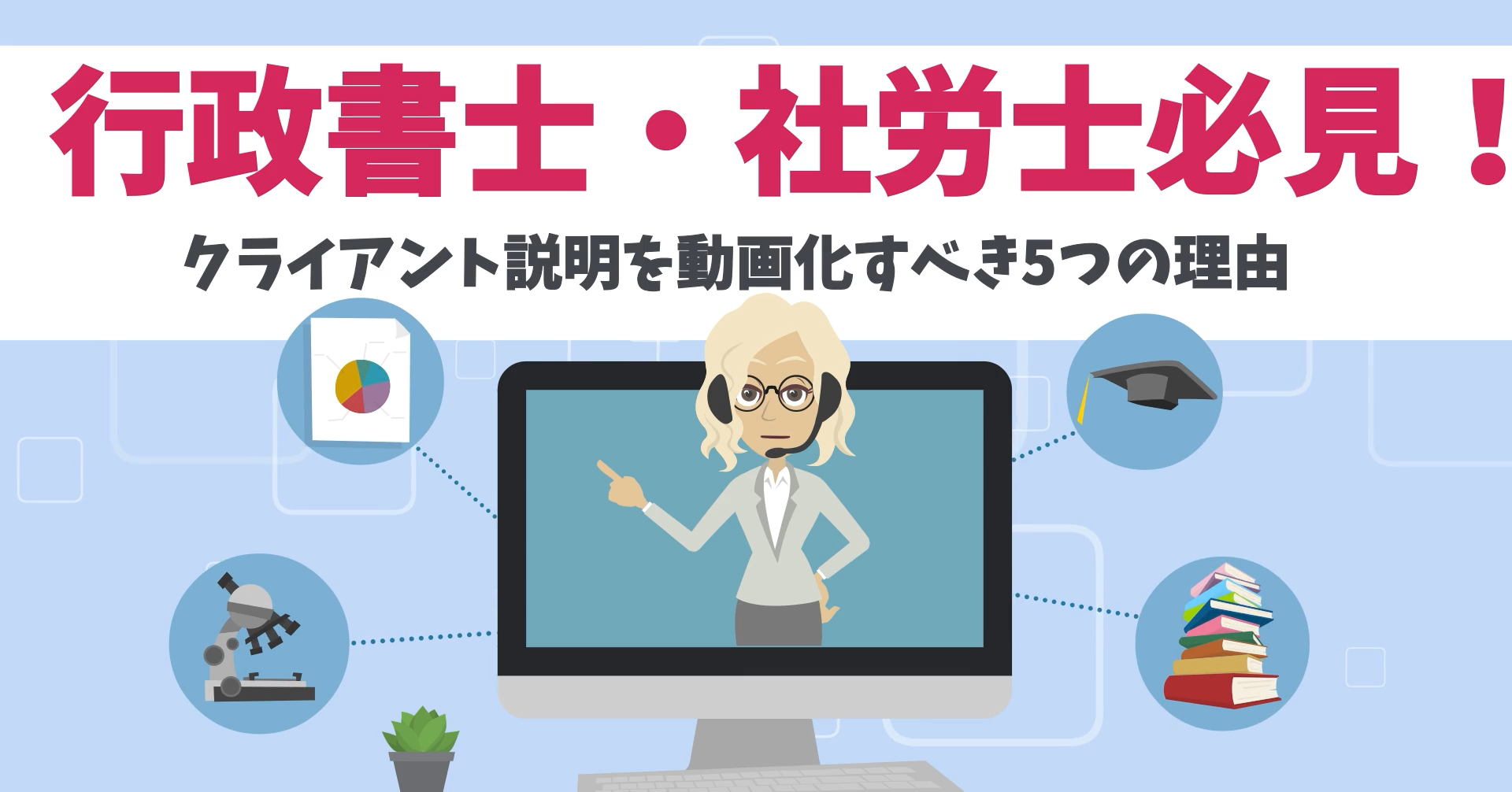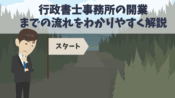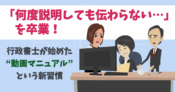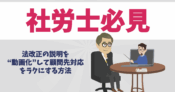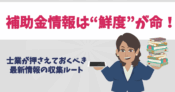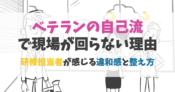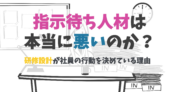行政書士・社労士が説明を動画化すべき5つの理由【業務効率化】
結論:説明の“繰り返し疲れ”は動画で解消できる
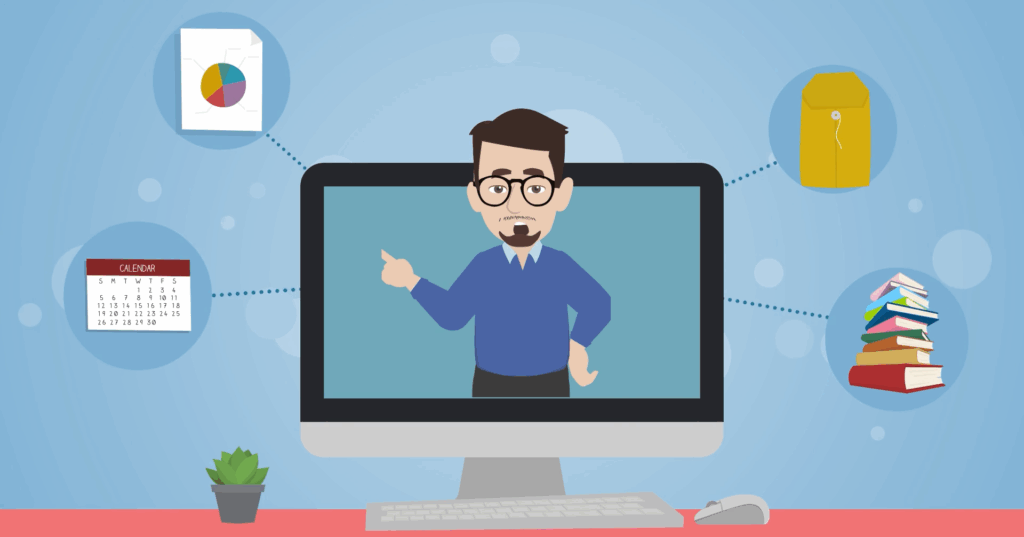
「同じ説明を何度もしなくてはいけない」──これは行政書士や社労士をはじめ、士業にとって共通する大きな悩みです。
顧問先に対して行う
- 制度の説明
- 手続きの流れの案内
- 契約書の読み合わせ
などは、どうしても“繰り返し”が多くなります。
しかも、一度で理解してもらえず、後日また同じ質問を受けることも珍しくありません。
こうした「繰り返しの説明業務」は、正直なところ時間もエネルギーも消耗します。
せっかく本業である書類作成や顧問先対応に集中したいのに、説明のたびに手が止まってしまう!
これでは生産性が上がらず、疲労感だけが積み重なっていきます。
しかし、この悩みは「動画化」することで一気に解消できるのです。
動画にしておけば、顧問先は必要なタイミングで何度でも視聴でき、士業側は同じ説明を繰り返す必要がなくなります。
つまり、動画は「自分の分身」として、24時間365日、同じクオリティで説明を代わりにしてくれる存在になるのです。
実際に動画を導入した事務所では、次のような効果が出ています。
- 説明の手間が大幅に減り、本業の業務に集中できるようになった
- 顧客が動画で繰り返し確認できるため、理解度が上がりトラブル防止につながった
このように、動画は単なる便利ツールではなく、士業にとっては「業務効率化」と「顧客満足度向上」を同時に実現する資産といえます。
そもそもなぜ「同じ説明」が繰り返されるのか?
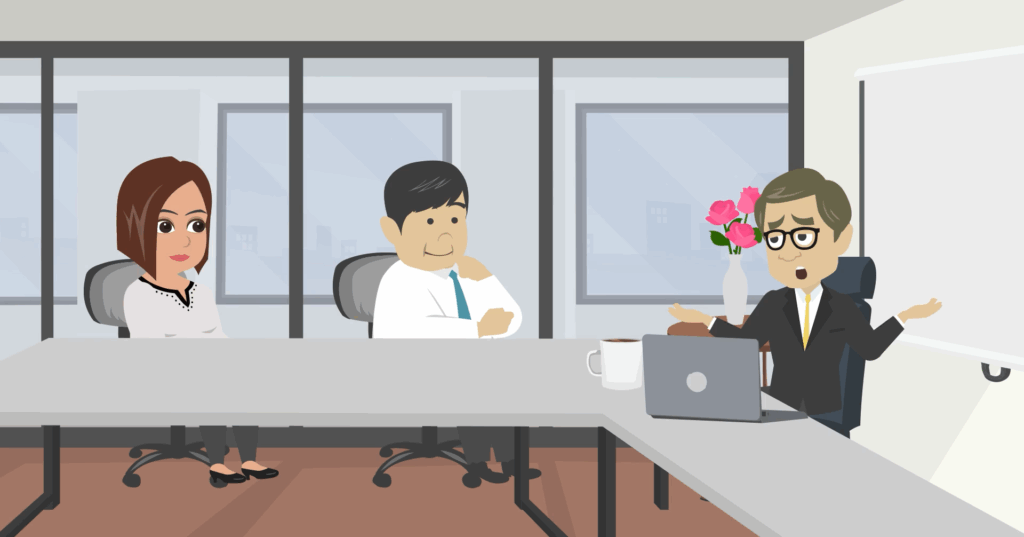
行政書士や社労士の仕事は、制度や法律に関わる“専門的な知識”が求められる場面が多いです。
そのため、顧問先やクライアントにとっては「一度聞いただけでは理解しきれない」ということがよく起こります。
行政書士のケース
行政書士が顧客に説明する内容には、例えば次のようなものがあります。
例
- 補助金申請の流れ
→ 提出書類の種類や期限、審査のポイントなど、複雑なステップを伴う - 契約書の注意点
→ 条文の意味やリスク回避の方法など、専門的な言い回しが多く登場する
これらは一見シンプルに思えても、法律知識がない顧客にとっては非常に理解しにくい内容です。
社労士のケース
社労士の場合も同様で、次のような説明を繰り返すことが多いでしょう。
例
- 就業規則の改定ポイント
→ 法改正に応じた変更点や、従業員に与える影響を具体的に説明する必要がある - 社会保険の手続き方法
→ 提出先や記入方法、提出期限など、細かなルールが多い
これらも「覚えたつもりでも実務で迷う」ことが多く、顧問先から再度質問される場面が頻繁に発生します。
なぜ繰り返しになるのか?
- 専門用語が多く、理解が追いつかない
- 人によって前提知識がバラバラ
- 時間が経つと忘れてしまう
- 担当者が変わるたびに説明が必要
このように、顧客側の事情で「同じ説明を繰り返さざるを得ない」状況が生まれるのです。
結果として、士業の先生は「先生、もう一度教えてください」という言葉を日常的に聞くことになります。
説明を動画化すべき5つの理由
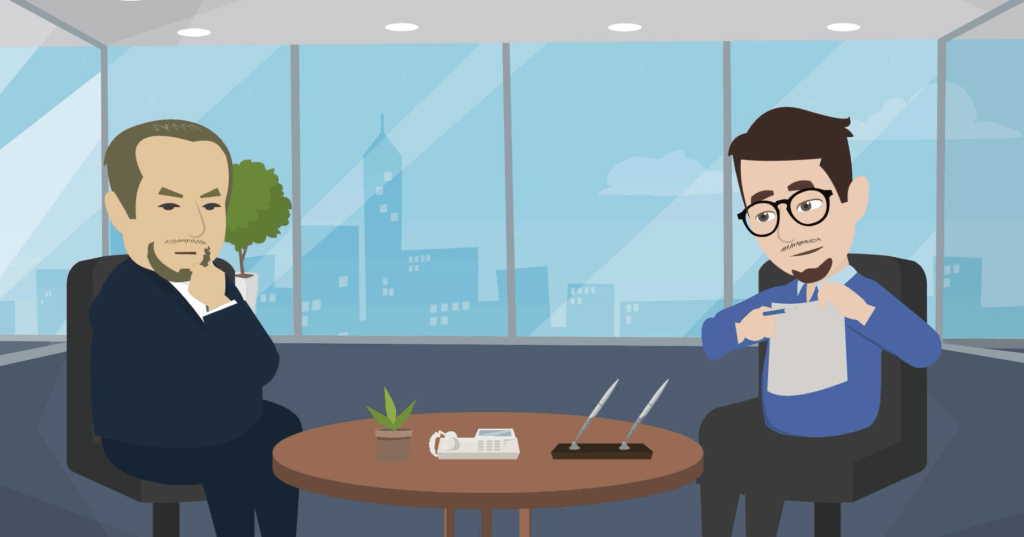
「繰り返し説明に疲れている…」という士業の先生にこそ、動画化は大きな武器になります。
ここでは、行政書士・社労士が説明を動画化すべき 5つの理由 を具体的に解説していきます。
理由①:24時間365日、同じクオリティで説明できる
人間が説明すると、どうしても“ブレ”が出ます。
忙しいときは早口になったり、省略してしまったり、気分によって説明の濃淡が変わることもあるでしょう。
しかし動画であれば、常に同じ内容を、同じクオリティで、何度でも届けることが可能です。
たとえば、補助金申請の流れや就業規則改定のポイントを動画にしておけば、顧客は「同じ説明」を安定して受けられます。
これは「わかりやすい先生」という印象を与えると同時に
先生自身の精神的負担を大きく減らす効果があります!
理由②:顧問先の“復習ツール”になる
「聞いたけど忘れた」「メモを取り損ねた」──顧客側のこうした事情は日常茶飯事です。
そのたびに「もう一度説明してください」と言われれば、士業側は貴重な時間を奪われてしまいます。
そこで役立つのが動画です。
動画なら顧客は自分のタイミングで再生し、繰り返し復習できます。
結果として、顧客の理解度が高まり、トラブルや誤解の防止にもつながるのです。
これは顧客にとっても「質問しやすい安心感」につながります。
つまり!顧客満足度の向上にも直結するのです!
理由③:新人スタッフの教育にも活用できる
動画は顧客向けだけでなく、事務所の内部教育ツールとしても役立ちます。
例えば社労士事務所であれば
- 助成金申請の流れ
- 社会保険手続きの入力方法
- よくある書類チェックの注意点
といった業務を新人スタッフに一から説明する必要があります。
しかし動画があれば、誰が教えても同じクオリティで学べる環境が作れます。
結果的に「教育の属人化」を防ぎ、ベテランスタッフの負担も軽減できます。
理由④:顧問先との信頼感アップ
ここまで丁寧に動画で説明してくれる事務所は少ない!
こう感じてもらえるだけで、顧客からの評価は大きく変わります
特に新規顧客への説明で動画を活用すると、
- 初回面談前に基本を理解してもらえる
- 打ち合わせ時間を有効に使える
- 「この先生はわかりやすい」と好印象を与えられる
といったメリットがあります。
これは単なる効率化にとどまらず、顧客との信頼関係を深める“差別化ポイント” になるのです。
理由⑤:自分の時間を確保できる
最終的に一番大きいメリットはここです。
同じ説明を繰り返す時間が減ることで、
- 本業(書類作成・顧問対応)に集中できる
- 新しい案件やサービス開発に時間を回せる
- 自分自身の休息時間を確保できる
といった効果が得られます。
つまり動画は単なる説明ツールではなく、先生の時間を守る“資産”になるのです!
実際の活用イメージ
では、実際に行政書士や社労士の先生がどのように動画を活用できるのか、具体例を見ていきましょう。
「難しそう」と感じるかもしれませんが、ポイントを押さえればすぐに取り入れられる内容ばかりです。
行政書士の場合:補助金申請の手順を動画化
行政書士業務で特に多いのが 補助金・助成金の申請サポート。
申請の流れは「準備 → 書類作成 → 提出 → 審査 → 結果通知」と複数のステップがあり、顧客にとっては覚えにくいものです。
ここを動画にまとめておけば、
メリット
- 顧客が必要なときに何度でも確認できる
- 申請期限や必要書類を見落としにくくなる
- 顧問先からの同じ質問が激減する
といったメリットが得られます。
つまり、動画は顧客にとって「わかりやすい案内ツール」、士業にとっては「説明の手間を減らす仕組み」となるのです。
社労士の場合:就業規則改定のポイントを動画化
社労士業務では、就業規則の改定や労務管理のルールを顧問先に説明する場面が頻繁にあります。
しかし「労働時間の上限規制」「育児介護休業法の改正」など、法律用語や改定内容を口頭だけで伝えるのは難しく、経営者が社員にうまく説明できないケースも多いです。
ここを動画化しておけば、
期待できる効果
- 経営者がそのまま社内研修や説明会で利用できる
- 従業員全員に同じ情報を一斉に共有できる
- 法改正対応の抜け漏れを防げる
といった効果が期待できます。
結果的に、顧問先の社内トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
YouTubeの限定公開を活用する
「動画をどこに置けばいいのか?」と迷う先生もいるかもしれません。
その場合は YouTubeの“限定公開”機能を使うのがおすすめです。
限定公開の機能
- 一般公開はされないので外部には見られない
- 顧問先にはURLを共有するだけで簡単に視聴可能
- 動画の概要欄に補足PDFや最新情報のリンクを追加できる
このように、限定公開を使えば「動画+資料」を組み合わせて提供でき、常に最新の情報を顧問先に届けられます。
注意点:動画はあくまで“補助ツール”

動画は非常に便利ですが、万能ではありません。
「すべてを動画で代替できる」と考えると、かって顧客対応の質を下げてしまう可能性があります。
ここでは、動画を活用するうえで意識しておきたい注意点を整理します!
個別相談は直接対応が必要
補助金や助成金の申請、就業規則の改定など、基本的な流れは動画で十分に説明できます。
しかし、顧問先ごとに事情が異なる具体的な相談に関しては、やはり直接対応が欠かせません。
たとえば、
- 「うちの会社の場合、この条件は当てはまりますか?」
- 「従業員の働き方を考えると、この規定はリスクになりませんか?」
といった相談は、ケースごとに答えが変わります。
動画は共通部分の説明に使い、個別の判断は直接のコミュニケーションで行うのがベストです。
法改正のニュアンスやリスク判断は口頭で伝える
士業の大きな役割のひとつに、最新の法改正情報を正しく伝えることがあります。
ただし、法改正の「グレーゾーン」や「今後の運用の流れ」など、言葉のニュアンスや背景事情を説明するには、動画よりも口頭の方が適しています。
顧問先は「リスクをどこまで許容するか」を先生の判断に委ねる場面も多く、その部分を動画だけでカバーするのは難しいのです。
動画は“便利な補助ツール”と考える
大切なのは、動画=先生の代わりではなく、先生を助ける補助ツールだという考え方です。
- 繰り返し発生する説明は動画に任せる
- 個別判断やリスクの助言は直接対応する
このバランスを取ることで、動画は顧問先との信頼関係を守りつつ、先生自身の時間を大きく節約してくれます。
まとめ:動画は“時間を生み出す資産”
行政書士や社労士にとって、「同じ説明を何度も繰り返す」という状況は避けがたい課題です。
補助金申請や就業規則の改定といった専門的な内容は、一度聞いただけでは理解が定着しにくく、結果的に顧問先から何度も同じ質問を受けることになります。
しかし、ここに動画を導入するだけで状況は大きく変わります。
動画がもたらす5つの効果
- 説明のブレをなくせる
常に一定の品質で伝えられるため、顧客にとっても安心材料になる。 - 顧問先の理解度が上がる
何度でも視聴できるので、復習ツールとして効果抜群。 - 新人教育にも活用できる
事務所内での教育を均一化し、スタッフの成長スピードを上げられる。 - 顧客との信頼関係が深まる
「ここまで丁寧に説明してくれる先生は少ない」という印象を与えられる。 - 自分の時間を守れる
繰り返し説明に割いていた時間を、本業や新しい業務に充てられる。
動画は“時間を生み出す資産”
これらの効果を踏まえると、動画は単なる説明ツールではなく、先生の時間を守り、新しい価値を生み出す「資産」といえます。
- 顧客対応の効率化
- 事務所内教育の効率化
- 信頼関係の強化
これらを同時に実現できるのは、動画ならではの強みです。
「説明に追われて時間が足りない」「同じ質問を何度もされて疲れている」──もしそんな悩みを抱えているなら、今こそ動画を活用するタイミングです。
動画はあなたの分身となり、24時間365日、同じクオリティで説明を続けてくれる最強のパートナーになります。
関連記事
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
などを行っています。
アニメで「視覚的にわかる」
ストーリーで「理解が深まる」
ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください!