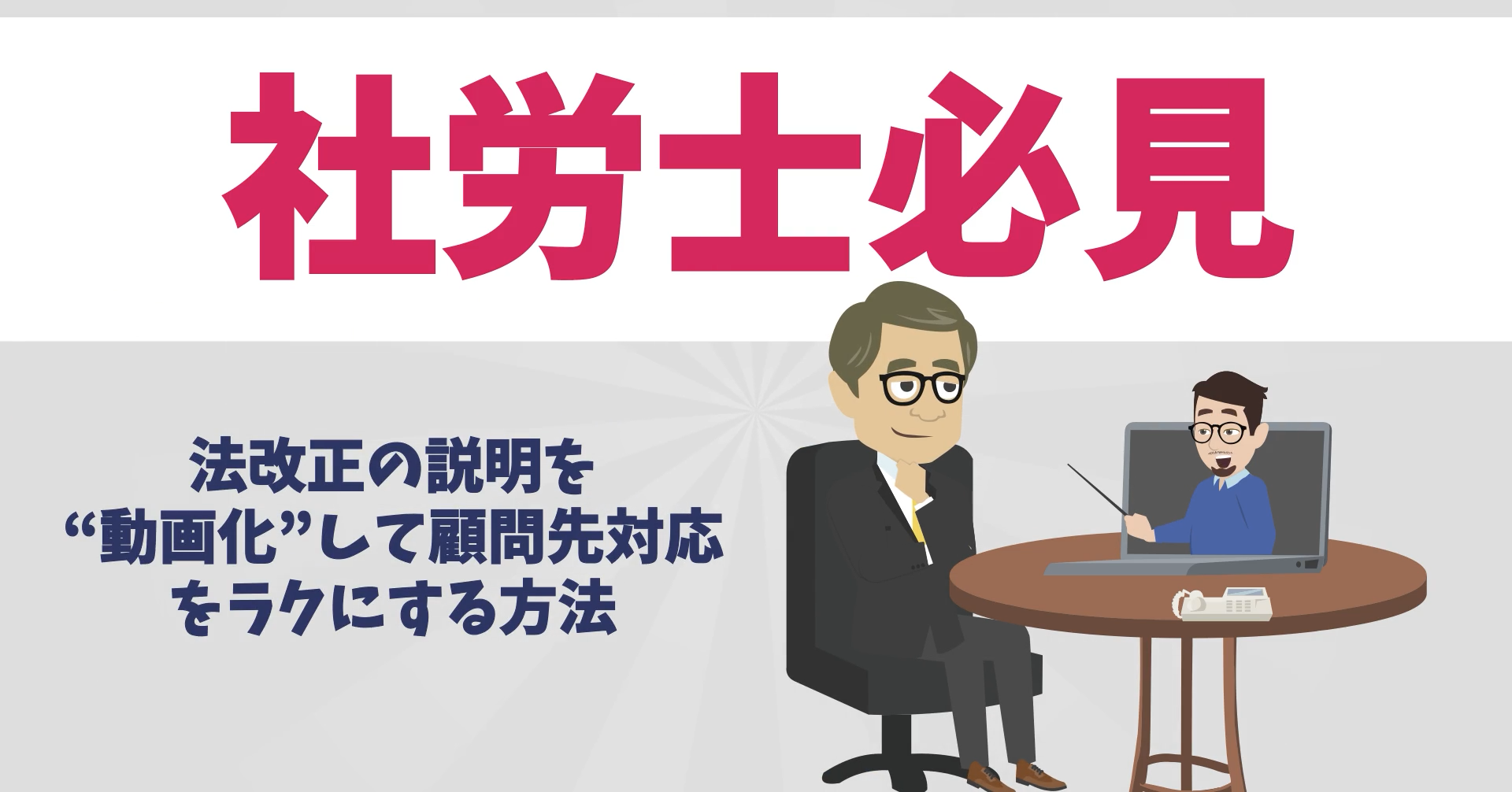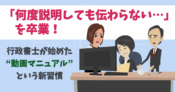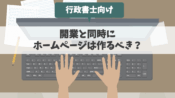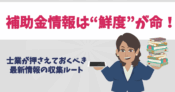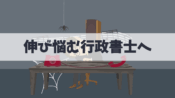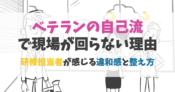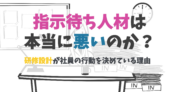社労士必見|法改正の説明を“動画化”して顧問先対応をラクにする方法
結論:法改正の説明は「動画」で仕組み化するのが最適解
社労士業務の中でも特に負担になりやすいのが「法改正対応」です。
顧問先から
「今回の変更ってどうなるんですか?」「結局、何をすればいいんですか?」
と同じような質問が繰り返されること、よくありますよね。
そのたびに一から説明していると、自分の時間も取られ、顧問料に見合わない労力をかけてしまうことも少なくありません。
そこでおすすめなのが 「法改正のアップデートを動画にまとめてしまう」 という仕組みづくりです。
動画にすることで、顧問先は「いつでも繰り返し見られる」ようになりますし、社労士側も「同じ説明を何度もする必要がない」状態を作れます。
つまり「説明疲れ」を減らしつつ、顧問サービスの価値を高めることができるのです!
なぜ社労士は「法改正対応」で疲れるのか?
毎年のように法改正があるたびに、正直ヘトヘトになる
多くの社労士の先生から、こんな声を聞きます。
では、なぜこれほどまでに法改正対応が負担になってしまうのでしょうか?
背景を整理してみると、大きく3つの要因が見えてきます。
1. 顧問先ごとに同じ説明を繰り返す
たとえば36協定の改正や助成金の変更があると、顧問先から次々と問い合わせが入ります。
しかも「内容は同じなのに、相手が違うから何度も話さないといけない」状況。
これは時間もエネルギーも大きく消耗します。
2. 資料作成の負担が大きい
パワーポイントやWordで改正点をまとめて、メールやセミナーで説明する。
しかし法改正は毎年のようにあるため、「せっかく作った資料もすぐに使えなくなる」こともしばしば。
3. 説明の“ニュアンス”がブレる
対面や電話での説明は、その場その場で表現が変わりがちです。
相手の理解度によって話し方を変えるのは良いことですが、一方で「説明の内容がバラつく」というリスクも。
結果として、顧問先の理解が浅くなり、後でトラブルにつながる可能性すらあります。
解決策:法改正の説明を「動画で資産化」する
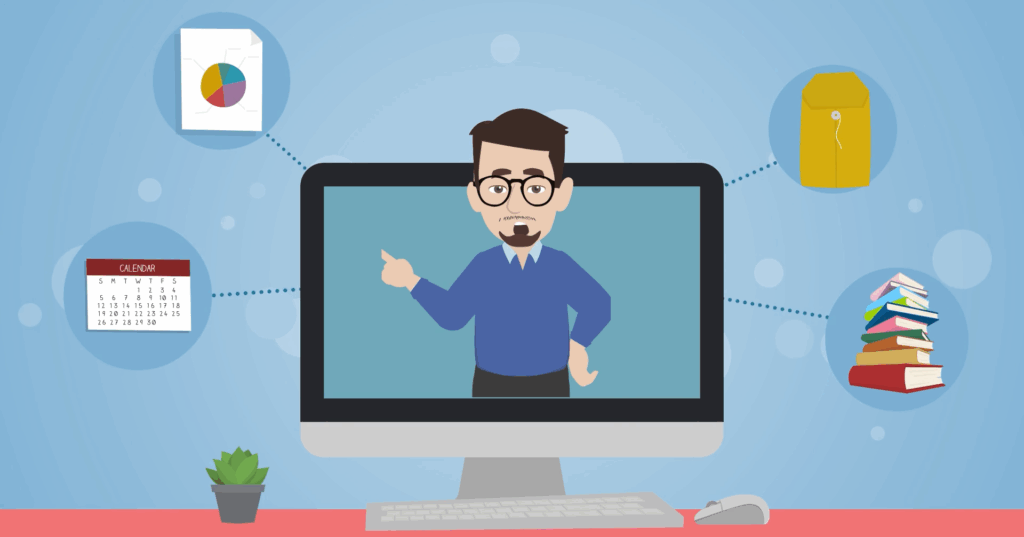
では、どうすればこの「説明疲れ」から解放されるのか?
答えはシンプルで、動画にまとめてしまうことです。
1. 一度作れば繰り返し使える
動画の最大の魅力は「一度作れば、何度でも使える」という点です。
たとえば、36協定の改正について3分の解説動画を用意したとしましょう。
その動画は顧問先が1社だけでなく、10社でも50社でも、リンクを送るだけで同じ説明を届けられます。
新しい顧問先が増えたけど、また同じ説明をしなきゃいけない…
という状況でも安心。
動画があれば、説明をゼロからやり直す必要がありません。
つまり、動画は“使い回しできる資産”になり、社労士にとって貴重な時間を取り戻してくれる存在になるのです。
2. 顧問先が「自分のタイミング」で学べる
忙しい経営者や人事担当者にとって、長時間の電話や対面での説明は大きな負担です。
- 今は会議中だから後で聞きたい
- 夜に時間ができたときに理解したい
といったニーズに、動画はぴったり応えてくれます。
YouTubeの限定公開やクラウド共有を使えば、スマホでもPCでもすぐに再生できます。
移動中の電車の中や、ちょっとしたすきま時間にチェックできるので、
- 聞き逃した
- 忘れてしまった
といったことも減ります。
顧問先にとっても「自分のペースで何度でも学べる安心感」があり、結果的に理解度が高まるのです。
3. 説明の質がブレない
対面や電話での説明は、そのときの相手や状況によって微妙に内容が変わってしまうことがあります。
昨日はこう言ったけど、今日はちょっと表現を変えてしまった///
という経験は、社労士なら誰もがあるのではないでしょうか。
動画なら、一度撮影・編集したものを全顧問先に同じように届けられます。
つまり、「誰に説明しても同じ内容」という状態を作ることができるのです。
これによって誤解や伝達ミスが減り、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
さらに「先生、あの部分をもう一度説明してもらえますか?」と聞かれても、動画を見直してもらえば済むので、双方にとって効率的です。
実際の活用例

動画活用といっても難しいことではありません。
具体的にどんな場面で使えるのかを見てみましょう。
例1:助成金改正のポイント解説
「今年はこの助成金が変更になり、対象要件がこう変わりました」という概要を、3分ほどの動画でまとめます。
申請のステップは別資料で補足しつつ、まずは「全体像を理解してもらう」ことに集中できます。
例2:36協定の新ルール案内
毎年のように変化がある労働時間関連の規制。
動画で「変わったポイント」「企業が取るべき対応」をわかりやすく解説しておけば、顧問先からの質問が減ります。
例3:定期的な“法改正アップデート便”
「四半期ごとに動画で改正情報をまとめて配信する」という形も有効です。
顧問先にとっては“最新情報を届けてくれる安心感”につながり、結果的に契約継続率の向上も期待できます。
動画を導入することで得られるメリット
改めて、動画を活用するメリットを整理しておきましょう。
- 同じ説明を何度もしなくてよくなる → 時間が浮く
- 顧問先が何度でも確認できる → 理解度UP
- 説明の質がブレない → トラブル防止
- 「先生にお願いして良かった」と思われる → 信頼度UP
- 顧問サービスの付加価値になる → 他事務所との差別化
つまり、社労士にとっても顧問先にとっても「Win-Win」な仕組みなのです!
どう始めればいい?シンプルな導入ステップ
「動画は便利そうだけど難しそう」と思う方もいるかもしれません。
ですが、最初はシンプルな形から始めれば大丈夫です。
動画化の導入ステップ
- テーマを決める
「助成金改正ポイント」「36協定の新ルール」など、まずは顧問先から質問が多いテーマを選びます。 - スライドを準備する
既に使っているセミナー資料や解説スライドをベースに。凝ったデザインは不要です。 - 音声を収録する
自分の声で解説を録音。ZoomやPowerPointでも簡単に可能です。 - 顧問先に共有する
YouTubeの限定公開や、クラウドストレージのリンクで配布すればOK。
これだけでも十分「説明疲れの軽減効果」が実感できます!
まとめ:法改正の説明は“動画で資産化”すべき
社労士が抱えやすい「法改正のたびに同じ説明を繰り返す」という悩み。
これは動画を活用することで大きく改善できます。
- 法改正対応は動画にまとめて“資産化”する
- 顧問先は「いつでも見直せる」安心感を得られる
- 社労士は「説明疲れ」から解放され、サービス価値もUPする
つまり、動画は単なるツールではなく、「説明を仕組み化する武器」になるのです。
これからの時代、法改正は減るどころかますます増えていきます。
だからこそ「法改正アップデートを動画で仕組み化」することが、社労士にとって最も効率的で、顧問先からも喜ばれる方法なのです。
関連記事
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
などを行っています。
アニメで「視覚的にわかる」
ストーリーで「理解が深まる」
ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
顧問先対応をもっと効率化したいと感じているなら、“動画で仕組み化”する第一歩を踏み出してみませんか?