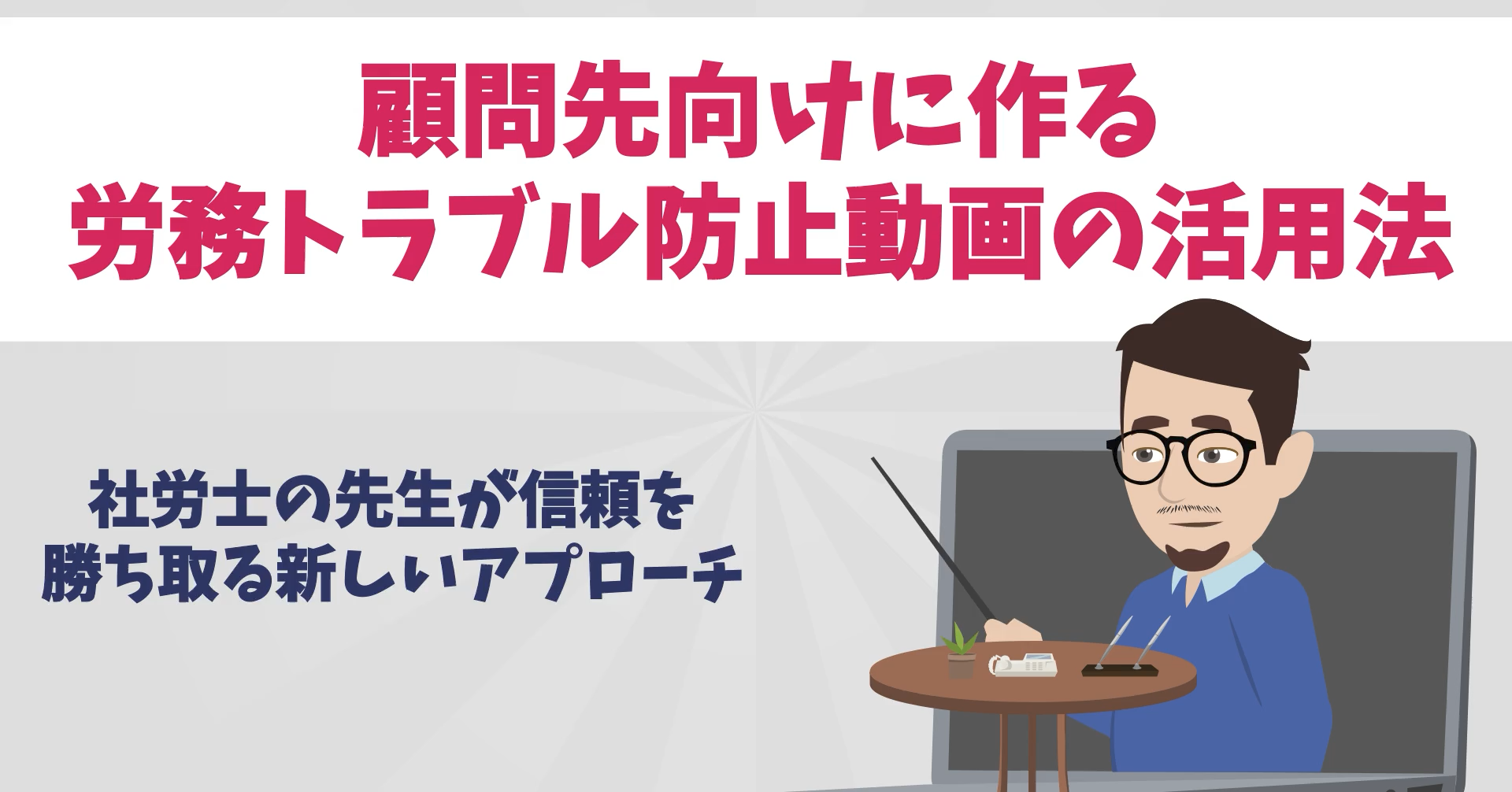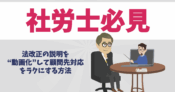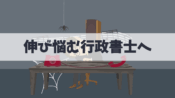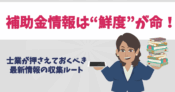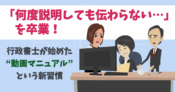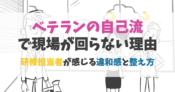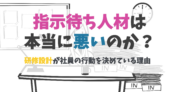顧問先向けに作る労務トラブル防止動画の活用法~社労士の先生が信頼を勝ち取る新しいアプローチ~
結論:労務トラブル防止には「動画」が効果的
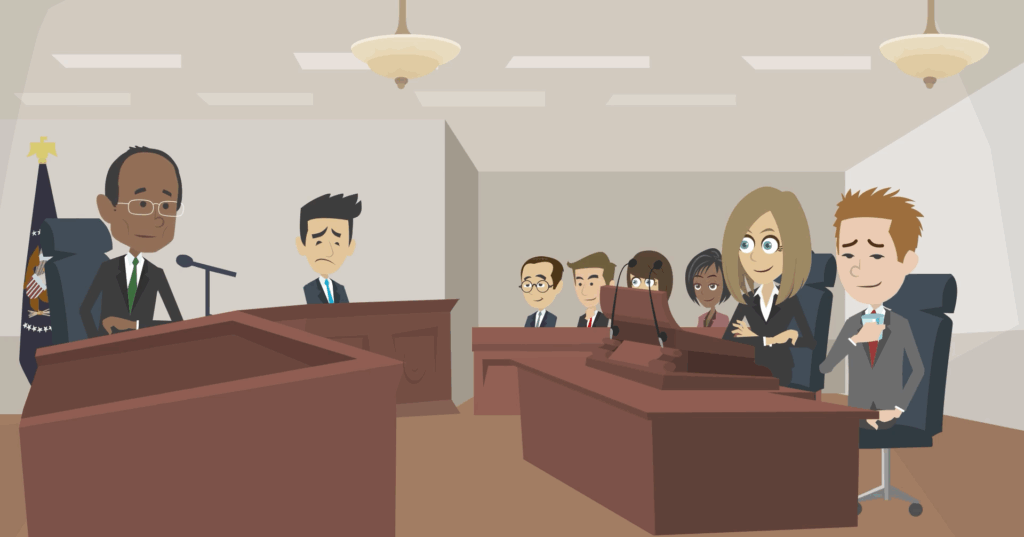
社労士の先生にとって、顧問先を守る上で最も大切な使命は、やはり 「労務トラブルを未然に防ぐこと」 ではないでしょうか。
労務トラブルは一度起きてしまうと、会社と社員の関係がこじれるだけでなく、裁判や行政対応にまで発展してしまうリスクがあります。
そうなると顧問先の経営に深刻なダメージを与えるだけでなく、「社労士がいても防げなかった」という残念な印象を持たれてしまうことも。
ところが現実には、多くの顧問先でこんな悩みが繰り返されています。
顧問先での悩み
- 就業規則や社内ルールを社員がきちんと読まない
- 「言った」「言っていない」で社内が揉める
- 同じ説明を何度も繰り返さなければならない
社労士の先生から見れば「ここを守らなければトラブルになる」とわかっていても、社員一人ひとりにルールを浸透させるのは簡単ではありません。
紙の資料や口頭説明だけでは限界があるのです。
そんなときに役立つのが、「動画を活用した労務トラブル防止の仕組み」 です!
動画は文字だけの資料に比べて理解しやすく、社員の記憶にも残りやすいのが特徴です。
さらに「視聴履歴が残る」「研修で使用したという証拠になる」という強みもあり、顧問先にとって安心材料となります。
つまり、社労士にとっての動画は単なる教育ツールではなく、「顧問サービスに付加価値を与える武器」 なのです。
顧問先に「この先生にお願いしていて良かった」と思ってもらえるポイントになり、長期的な信頼関係の構築にもつながっていきます。
なぜ「動画」が有効なのか?

1. 書類は読まれない
顧問先に就業規則や社内ルールを整備しても、「社員がきちんと読んで理解しているか」というと、実際にはそうでもありません。
多くの社員は入社時に就業規則を渡されても、その分厚さに圧倒されてしまい、細かい内容までは読み込まないのが現実です。
厚生労働省の調査によれば、「就業規則の内容をしっかり把握している社員」は2割程度 にとどまるといわれています。
つまり8割近くの社員は
なんとなくあるのは知っているけど、具体的なルールまでは理解していない…
状態です。
これではせっかく社労士が労力をかけて作成した規則も、現場で生かされず、トラブル防止の力を発揮できません。
やはり「文字で渡すだけ」ではルールは定着しないのです!
2. 繰り返し視聴できる
口頭で伝えた内容は、一度聞いただけでは忘れてしまうことが多いものです。
特に入社直後の新人社員は覚えることが山ほどあるため、労務ルールの説明は記憶から抜け落ちやすい傾向があります。
その点、動画であれば「必要なときに何度でも繰り返し視聴できる」ため、理解度が高まりやすくなります。
例えば
- 残業申請のやり方
- ハラスメント相談の窓口
など、細かい手順を口頭で毎回説明していたら大きな負担になりますが、動画にしておけば社員自身が自主的に確認できます。
繰り返し学べる仕組みを用意することで、顧問先は教育の効率を大きく高めることができるのです!
3. 証拠として残せる
もうひとつ、動画ならではのメリットが「証拠として残せること」です。
顧問先が動画を研修で活用すれば、「社員に教育を実施した」というエビデンス(証拠) になります。
たとえばハラスメント研修を実施した場合、後から
- そのルールは知らなかった
- 研修を受けていない
と社員に言われても、動画を使って周知していた記録があれば会社を守る材料になります。
労務トラブルが起きた際に「周知していなかった」と言われにくくなることは、顧問先にとって大きな安心感につながります。
4. コスト削減にもつながる
最後に、動画には「コスト削減効果」があります。
社長や人事担当者が同じ説明を社員に繰り返していると、その時間だけで膨大なコストがかかります。
特に社員数が多い企業では、説明の回数が増えるほど負担も大きくなります。
動画であれば 一度作ってしまえば、何度でも繰り返し使える ため、長期的に見れば大きなコスト削減効果を生み出します。
さらに「誰が説明しても内容がブレない」というメリットもあるため、教育の質を一定に保ちながら効率化を実現できます。
顧問先にとっては
- 人件費の削減
- 教育の均一化
という二重のメリットが得られるのです。
顧問先に提供できる動画テーマ例
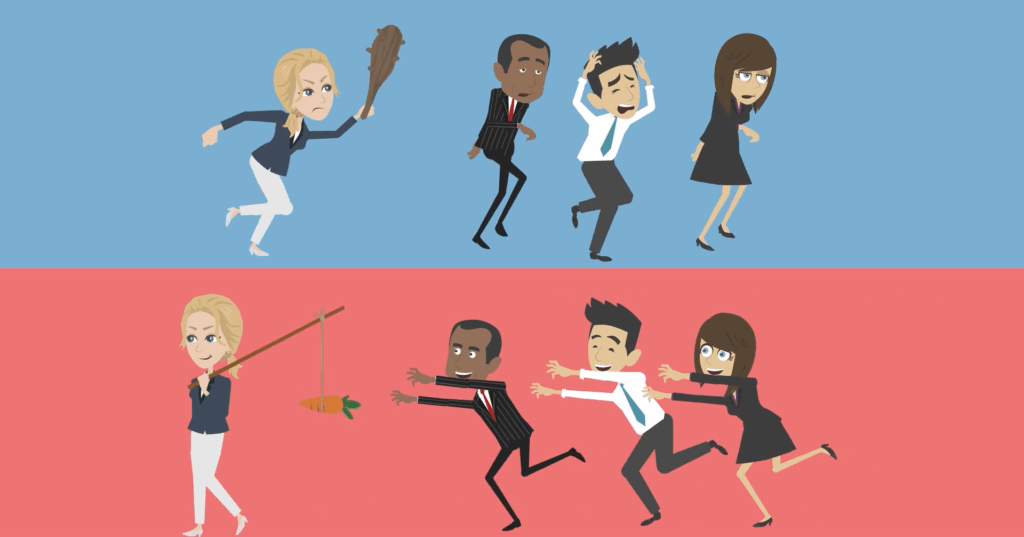
「労務トラブル防止」に直結する動画には、いくつかの“定番テーマ”があります。
これらは実際にトラブルの原因になりやすい分野でもあり、顧問先からのニーズが高いポイントです。
社労士の先生が動画教材として整備しておけば、顧問先にとっても「トラブルを予防できる安心感」につながります。
1. ハラスメント防止
もっとも多くの企業で課題になっているのが ハラスメント防止 です。
パワハラやセクハラの線引きは人によって認識が異なるため
- 冗談のつもりだった。
- 教育の一環だった。
という言い訳からトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
動画では、ありがちな事例をアニメーションで紹介することで、社員が「自分ごと」としてイメージしやすくなります。
さらに、具体的に 「やってはいけない行動」 を解説すれば、曖昧だった境界線がクリアになります。
加えて、社内や外部の 相談窓口の案内 を動画の最後に入れておくことで、実際に問題が起きたときに行動に移しやすくなるのです。
2. 残業・勤怠ルール
次に多いテーマが 残業や勤怠管理のルール です。
特に中小企業では、36協定の意味やルールが正しく理解されていないことが少なくありません。
社員に、
残業は自己判断でやっても良い!
と思われてしまうと、サービス残業や過労につながり、後々大きなリスクを抱えることになります。
動画で 36協定の基本 を解説し、サービス残業が会社にどのような影響を与えるのかを事例を交えて伝えることで、社員の意識は大きく変わります。
さらに、勤怠記録の付け方や報告の手順を動画で示せば、曖昧な運用を防ぎ、会社全体の労務リスクを下げることができます。
3. SNSトラブル防止
ここ数年で急増しているのが SNSに関するトラブル です。
社員の軽率な投稿が炎上し、企業のイメージを傷つけてしまうケースは珍しくありません。
また、顧客情報や社内資料を誤って公開してしまうリスクもあります。
SNSの怖さは、ひとたび炎上すると一気に拡散し、会社の信用を失ってしまうこと。
そのため、動画では実際にあった事例を紹介しつつ、「社員がSNSを利用する際のルール」 をまとめて周知するのが効果的です。
特に若手社員やアルバイトスタッフなど、SNSに慣れた世代にこそ響くテーマといえるでしょう!
4. 安全衛生・労災対応
最後に取り上げたいのが 安全衛生と労災対応 です。
製造業や建設業ではもちろん、オフィスワークでも転倒や腰痛などの労災は発生します。
ところが、労災が起きたときの報告手順や初動対応を社員が知らないケースも多く、結果的に会社が不利な立場に立たされることもあります。
動画では、現場での安全確認の手順を映像で見せることで、「自分もやらなければ」と意識づけができます。
また、労災が発生した際に 「まず誰に、どのように報告するか」 を具体的に解説すれば、いざというときの対応力が高まります。
さらに「報告を怠った場合のリスク」まで触れることで、社員の行動を強く後押しできるのです。
これらのテーマは、顧問先の業種や規模に合わせて内容をカスタマイズできます。
そして何より重要なのは、社労士の先生が作るからこそ「法律に基づいた正しい内容」で信頼性が高い という点です。
一般的な研修会社の教材と比べても、法的裏付けがある動画は顧問先にとって心強い存在となります!
活用シーン:動画が顧問先でどう役立つか?

1. 新入社員研修に活用
顧問先にとって、新入社員への教育は「最初の定着率を大きく左右するポイント」です。
入社直後の新人は覚えることが多く、会社のルールや労務管理の基本が頭に入りにくい時期でもあります。そこで役立つのが 「動画を使った研修」 です。
動画なら、「うちのルールはこうですよ」と一度に分かりやすく伝えることができます。
また、研修のたびに人事担当や社労士が直接説明する必要がなくなるため、説明の内容にブレが出ません。
結果として、新人が「何を守れば良いか」を早い段階で理解でき、定着率アップにもつながります!
2. 定期配信で「教育の見える化」
労務トラブル防止は「一度教育すれば終わり」というものではありません。
時間が経てば社員はルールを忘れてしまいますし、法改正や会社の制度変更に合わせてアップデートも必要です。
その点、動画を半年に1回、あるいは1年に1回のペースで定期的に配信すれば、「継続的に教育している」ことを可視化できます。
これは労務管理上のリスクを減らすだけでなく、顧問先にとっては
会社として社員教育に力を入れている!!
というアピールにもなります。
社員にとっても「定期的に学べる場がある」と感じられるため、ルールを自分事として捉えやすくなるのです。
3. トラブル発生時の再確認
どんなに教育をしていても、トラブルがゼロになることはありません。
問題が発生したときに、社員が慌てて誤った行動を取ってしまうと、事態はさらに悪化します。
そこで役立つのが 「動画を見返せる仕組み」 です。
- 労災が起きたときは誰に連絡するのか
- ハラスメントを受けたときの相談窓口はどこか
など、正しい対応が動画で確認できれば、社員は落ち着いて行動できます。
また、会社としても「再度教育を徹底した」という形で証拠を残せるため、二次的なトラブル防止にもつながります。
動画活用の注意点
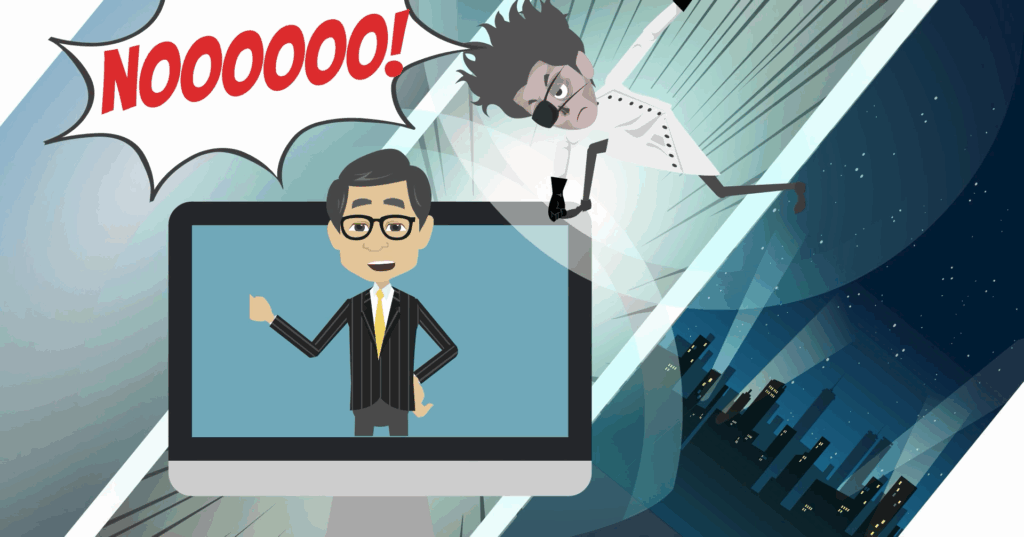
便利な動画ですが、万能ではありません。
労務トラブル防止に効果を発揮する一方で、いくつかの注意点を理解した上で活用しないと、逆にリスクを生んでしまうこともあります。
ここでは特に気を付けたいポイントを整理しておきましょう!
1. 法改正ごとにアップデートが必要
労働基準法や関連する労務ルールは、数年ごとに改正されることが珍しくありません。
たとえば
- 「残業時間の上限規制」
- 「パワハラ防止法」
など、ここ数年だけでも大きな法改正が次々と施行されています。
もし古いままの内容で動画を使い続けてしまうと、社員に誤った知識を広めることになり、かえってトラブルの火種になる可能性があります。
そのため動画は「作って終わり」ではなく、法改正や制度変更があるたびにアップデートすることが必須です。
2. 個別判断は動画ではカバーできない
動画は基本的なルールや考え方を社員に周知するにはとても効果的です。
しかし、実際の労務トラブルは「ケースバイケース」であり、細かな事情や背景を踏まえて判断しなければならない場面が少なくありません。
たとえば
- 「残業命令を拒否できるのか」
- 「育児休業からの復職をどうサポートするか」
などは、会社ごと・社員ごとに事情が異なります。
こうした問題は動画だけで解決できるものではなく、必ず社労士による個別相談や顧問対応が必要になります。
つまり、動画は“万能の解決策”ではなく、あくまで基礎教育の補助ツール と考えることが大切です。
3. 長すぎる動画はNG
もうひとつ注意したいのが、動画の長さです。
「せっかくだから詳しく解説しよう」と意気込んで10分以上の動画を作ってしまうと、社員が途中で集中力を失い、最後まで視聴してもらえないことが多くなります。
効果的なのは 3〜5分程度の短い動画 にまとめること。
1本あたりをコンパクトにしておけば、隙間時間に気軽に視聴できるため、社内への浸透率も高まります。
どうしても内容が多い場合は、テーマごとに複数の動画に分けてシリーズ化するのがおすすめです!
社労士にとってのメリット
動画は顧問先のためだけのものではありません。
実は、社労士の先生ご自身にとっても大きな武器となります。むしろ、上手に活用すれば 「時間」と「信頼」を同時に生み出す資産」 になってくれるのです。
まず、動画を導入することで 顧問サービスの付加価値が高まります。
就業規則の作成や相談対応はどの社労士事務所でも行っていますが、そこに「トラブル防止動画」をプラスできると、顧問先から見たときのサービスの幅が一気に広がります。
単なる規程作成や書類業務にとどまらず、「教育や周知までサポートしてくれる先生」として差別化できるのです。
さらに、これは 他の事務所との差別化 にも直結します。
競合する社労士が増えている中で、
動画を活用して顧問先を支援している!
という取り組みは、顧問契約を維持・拡大する上で大きな強みになります。
特に経営者は「人材教育の仕組み」を重視しているため、提案の説得力が増すのです。
そして何より、動画を導入することで 同じ説明を繰り返す手間が減る のも大きなポイントです。
- 「ハラスメント研修」
- 「勤怠ルール」
- 「労災対応」
など、顧問先から何度も聞かれる質問を動画にまとめておけば、先生の時間は大幅に節約されます。
その分、本来のコンサルティング業務や新規顧客開拓に時間を使えるようになります。
結果的に、顧問先からは 「先生にお願いしてよかった」と信頼が強まる ことにつながります。
動画は一度作れば長く使えるため、繰り返し顧問先の役に立ち続ける“無形資産”になります。
つまり、動画は顧問先の教育を助けるだけでなく、社労士の先生ご自身の「時間を生み出す資産」 でもあるのです。
まとめ:動画は「顧問先との信頼を強化する資産」
労務トラブルを防ぐために、社労士が顧問先に提供できるサポートは
- 「規程を作成すること」
- 「相談に応じること」
だけにとどまりません。
それらはもちろん大切ですが、実際に現場の社員へルールを浸透させ、守ってもらわなければトラブルは減りません。
そこで効果を発揮するのが、動画を通じて教育を仕組み化する取り組み です。
動画を導入すれば、顧問先のトラブル防止力は格段に高まり、社内の安心感もぐっと強まります。
具体的には、次のようなメリットがあります。
- 社員がルールを理解しやすい
文字や口頭の説明よりも、動画の方がイメージしやすく記憶に残ります。社員一人ひとりがルールを“自分ごと”として理解できるのです。 - 教育の証拠が残る
動画を研修に組み込めば、「社員に周知・教育を実施した」という確かなエビデンス(証拠)が残ります。トラブル発生時に「知らなかった」と言われるリスクを軽減できます。 - 顧問先に安心を届けられる
「ルールが社員にきちんと伝わっている」という安心感は、経営者にとって大きな支えになります。労務トラブルに対する不安が減り、社労士への信頼も高まります。 - 社労士のサービス価値が上がる
規程や相談対応だけではなく、動画による教育までサポートできることは、他の事務所との差別化になります。顧問契約の更新率や紹介につながる可能性も広がります。
つまり、動画は「単なる便利なツール」ではありません。
顧問先と社労士との信頼関係を深め、長期的に顧問先を守るための“資産” なのです。のです!
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
などを行っています。
アニメで「視覚的にわかる」
ストーリーで「理解が深まる」
ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください!