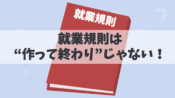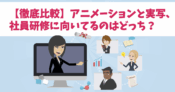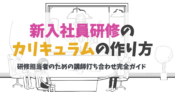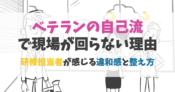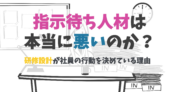なぜ研修は伝わらない?説明のバラつきに要注意
「せっかく時間とお金をかけて研修をしているのに、現場でまったく活かされていない…」
こんな悩み、ありませんか?
実はこれ、多くの企業が抱えている共通の問題なんです。
その裏にある“見落とされがちな原因”が、実は。。。
「説明のバラつき」
今回はこの「説明のバラつき」がなぜ研修の定着を妨げてしまうのか、そしてどう対策していけばいいのかを、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
そもそも「説明のバラつき」って?
簡単に言うと、同じ内容の研修でも、教える人によって言い方や伝え方が違ってしまうこと。
たとえば、あるマニュアルがあっても、
先輩Aさんは「このへんは臨機応変でいいよ」
と言い
先輩Bさんは「いや、絶対この手順じゃなきゃダメ」
と言う。
受け取る側の新人からすると、「結局どっち?」と混乱してしまいますよね。
この“ちょっとしたズレ”が積み重なることで、研修の定着率がガクッと下がるんです。
説明がズレるのはなぜ?
ではなぜ、こんなにも「教える内容」がズレてしまうのでしょうか。
理由は大きく3つあります。
1. 研修担当者の解釈がまちまち
同じ資料を見ても、捉え方が違えば伝え方も変わります。
「この資料、たぶんこういう意味だよね?」
と“なんとなく”で教えてしまうと、違う人が見るとまた違う解釈になってしまいます。
たとえば、ある研修資料に、お客様から電話があったら
ヒアリング → 内容確認 → 担当者へ引き継ぎ
と書かれていたとします。
これを見たAさんは
「お客様が困っていることをざっくり聞いてから担当者に回せばいい」
と理解して新人に教えます。
一方でBさんは
「聞き漏れがないように必ずヒアリングシートの全項目を埋めてから引き継ぐこと」
と教えます。
このように同じ資料を使っているのに、受ける印象や行動がまったく違ってしまいます。
新人からすれば、
「どっちを信じたらいいの?」
となりますよね。
こうした“ちょっとした解釈の違い”が積み重なると、現場での判断や行動にズレが生じてしまうんです。
2. 教える人がその場の雰囲気で補足してしまう
「研修資料には書いてないけど、実はこういうことがあってね…」
という“現場トーク”。
親切心ではあるんですが、これは場合によっては混乱のもと。
たとえば、マニュアルには
「電話対応は3コール以内に出る」
と書いてあるのに、教える人が
「でもウチはだいたい5コールぐらいまでなら大丈夫」
と言ってしまう。
新人からすると「え、どっちが正解?」と、これまた迷ってしまいますよね。
マニュアルはマニュアル、現場は現場でルールが違う…となると、新人は“正しい判断軸”を持てず、不安やミスにつながります。
3. 経験に頼りすぎる
3. 経験に頼りすぎる
ベテランほど「これくらい説明しなくても伝わるだろう」と思いがちです。
でも、新人にとっては見るものすべてが初体験。
たとえば、
「この作業は感覚でやって大丈夫」
と言われても、そもそもその“感覚”が分からない。
どこまでやればOKなのか、自分で判断できずに戸惑ってしまいます。
私自信クリエイティブな仕事柄、上司に言われ何が正解かわからず戸惑った経験があります。
経験は大きな武器ですが、それを言葉にして丁寧に伝えることも同じくらい大切です。
「見れば分かるでしょ」は、教える側の思い込みかもしれません。
説明のバラつきが生む“現場のズレ”
こういったバラつきが現場でどう影響してくるかというと…
- 対応が人によって違う
- クレーム対応が属人化する
- チームでの意思統一が取れない
- 「教え方がバラバラ」と新人が不信感を持つ
最悪の場合、
「ちゃんと研修したのにミスが出た」
という“責任の押し付け合い”にもなりかねません。
解決策は「説明の統一化」
じゃあ、どうすれば説明のバラつきを無くしてミスをなくせるのか。
ポイントは次の3つです。
1. “教える内容”を見える化する
テキストやマニュアルに落とし込むのはもちろんですが、「どの言い回しで」「どこまで説明するか」も具体的に言語化することが重要です。
たとえば、
- 「お客様にはこの順で話す」
- 「この場面ではAではなくBを優先する」
など、状況別に細かくルールを決めておくことが重要です。
2. ロールプレイやケーススタディを取り入れる
文章だけでは伝わりにくい“空気感”や“対応のコツ”は、実際のやり取りを通して練習するのがベスト。
「このケースではどう返す?」とチームで共有することで、説明のズレが減ります。
3. 全員が同じ研修を受ける
誰か一人が内容を聞いて他の人に伝える「伝言ゲーム方式」は、バラつきの温床です。
最初から全員が同じ研修を受けるようにすれば、スタート地点のズレがなくなります。
ここで大事なのは、
「全員に一度に研修を受けさせる」
ことだけでなく、
「同じコンテンツを何度でも見直せるようにしておく」
ことです。
例えば、録画された研修映像を共有しておけば、新人が後から復習できるだけでなく、ベテラン社員も「言い回し」や「説明の順番」を確認することができます。
また、新しく入った人にも同じ教材を渡せば、
「この人には詳しく教えたのに、この人には時間がなかった」
などの不公平感もなくなります。
研修の内容が“流動的”ではなく、“固定された基準”として共有されることで、バラつきのリスクは大きく減ります。
よくある勘違いベスト3
1. 「マニュアルがあれば大丈夫」
マニュアルはあっても、“読みやすさ”や“使いやすさ”がないと意味がない。 内容が古かったり、現場で使えなかったりすると、結局誰も見なくなります。
2. 「経験者に任せれば自然に教えてくれる」
ベテランだから教えるのが上手とは限らない。 逆に「自分流」が強すぎると、バラつきの原因になります。
3. 「1回教えれば十分」
人は一度で覚えられません。 繰り返し・実践・フィードバックがあってこそ、定着します。
今日からできる“説明の整え方”ミニアクション5つ
- 共通用語集をつくる:チーム内で使う言葉の定義をそろえるだけでも混乱が減ります。
- “やってはいけない”ことを明文化する:曖昧なNGルールは事故の元。
- 現場の声を拾ってマニュアルをアップデート:定期的に見直すクセを。
- 教えるときの「型」を作る:OJTでも教え方のテンプレがあるとラク。
- 教える人へのフォローも忘れない:「新人の悩みを聞いてあげてる?」を振り返ってみましょう。
この5つのアクションは、どれも小さな一歩かもしれませんが、積み重ねれば「伝わる説明」への大きな土台になります。
教える側・教わる側のストレスを減らすためにも、まずはできるところから一つずつ取り入れてみましょう。
まとめ:伝え方に“バラつき”がある限り、研修は定着しない
研修を「一度やったら終わり」にせず、「伝わるように整える」こと。
これが、真に意味のある研修を実現する第一歩です。
説明の仕方、伝える順序、言葉選び。
そうした“ちょっとした部分”を揃えるだけで、現場のチームワークや新人の理解度は格段に変わります。
に言えば、説明を整えるだけで、
- 新人の定着率アップ
- 現場のミス減少
- お客様対応の質の向上
など、さまざまな効果が出てくるんです。
もし「うちの研修、なんかうまくいかないな…」と感じているなら、
一度「説明のバラつき」がないか、ぜひ見直してみてください。
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
この研修の課題、テーマはアニメーション動画との相性抜群です。
視覚で伝える・ストーリーで理解させる・ナレーションで補完する、という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください。