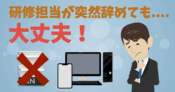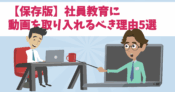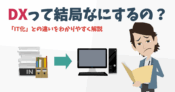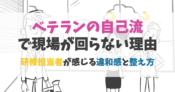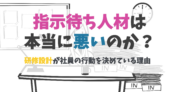研修担当が辞めても困らない!教育動画の威力とは?
「教育は“人”から“仕組み”へ。教育動画で“いつでも・誰でも・同じ質”を実現しよう」
属人化からの脱却が、未来の組織をつくります。
はじめに:突然の“辞めます”に震えた若きあの頃
ある日、いつも通りオフィスに出社すると、研修担当さんから放ったこの言葉。
「実は、今月いっぱいで辞めることになりまして…」
WHAT!?
そう思った方、きっと私だけではない。
研修担当のAさんはおしゃべりが上手でランチなんかでもご一緒すると楽しく時間をご一緒できる人でした。
社内でも“伝える力”に長けた人で、新人研修やマニュアル作成も一手に担っていた存在。
人事でもなく、教育専門でもないけど、なぜか「あの人がいれば新入社員が入ってきても安心」という絶対的な安心感がありました。
でも、その人が辞めてしまう。
それはつまり、「教える人がいなくなる」ってこと。
だれが新人さんを教えるんじゃー!!
っと、この日から社内は軽くパニック。
「じゃあ次、誰が研修やるの?」
「教え方なんて知らないよ…」
「マニュアル読んだらいいだけ?」
—— まさに、教育の属人化が招いた混乱でした。
2. なぜ教育は属人化しがちなのか?
そもそも、なぜ教育って属人化するでしょう?
理由はとてもシンプルで、こんな構図があるからです。
- 新人が入ってくる
- とりあえず現場に配属
- ベテランが“口頭で”教える
- 現場の人も忙しい
- 「あとは見て覚えて」で終了
はい、ありがちなOJTパターンですね。
OJT(職場内訓練)は確かに効果的な面もあります。
実務で学べるし、現場の雰囲気もつかめる。
でも、これが慢性化すると……
- 教える人によって伝え方がバラバラ
- 見て覚える=理解できてるとは限らない
- 教える側の“善意とスキル”に依存する
つまり、「個人の力量任せ」な仕組みになってしまうんです。
そしてその結果、「あの人がいないと研修が回らない」状態が生まれます。
3. 研修担当が辞めたら、何が困る?
実際に研修担当が抜けたとき、社内ではどんな問題が起こるのか?
ネット上のリアルな声を集めてみましたのでご紹介します。
- 「え、何から教えればいいのか分からない」
- 「研修資料、どこに保存してあるの?」
- 「引き継ぎってこのExcelだけ…?」
- 「Aさんがいないと雰囲気がピリつく」
つまり、
- ノウハウが“個人の頭の中”にしかない
- 引き継ぎが曖昧すぎて中身が分からない
- 新人が何を教わったか見えない
- 指導者が変わるたびに内容がズレる
結果、新人が混乱し、育つスピードが落ちます。
せっかくの採用コストが、ここで無駄になってしまう。
あと私が経験したのはやっぱり人(研修する側)によって伝え方が違うと、受け取り方の理解もバラバラになってしまって、研修後にもう一度教え直さないといけなくなるという状況が多かったです。
4. 解決策は「教育をコンテンツ化」すること
この問題、実は“あること”をするだけで一気に解決に近づきます。
それが——「教育動画を作ること」です。
なぜ動画なのか?
- 同じ内容を、同じ順番で、同じ表情で届けられる
- いつでも、どこでも、何回でも見返せる
- 視覚+聴覚で情報を伝えられるから理解が深まる
例えば、同じ「接客のコツ」を教えるとしても、
テキストだと「丁寧に対応しましょう」としか書けない。
でも、動画なら——
- 声のトーン
- 表情
- タイミング
- 間の取り方
など、「文章では伝えきれない部分」がそのまま届けられます。
これはOJTにかなり近い感覚なんですよ。
5. よくある誤解:「動画にしたって結局見ないでしょ?」
「動画にしたって、どうせ誰も見ないよ…」
この声、めちゃくちゃよく聞きます。
でも実はこれ、仕組み”がないから起きる問題なんです。
自発的に見てもらう工夫、してますか?
- 動画の最後にミニクイズを用意する
- 実務とリンクした構成(「この業務前にこの動画を見る」)
- 1本3分以内のショート形式で細かく分ける
この3つだけでも、動画の視聴率はグッと上がります。
とくに「長い動画はNG」。5分超えると集中力が切れます。
動画教育にありがちな失敗は、「長くて、つまらなくて、実務と関係ない」という三拍子。
ここを外すと、せっかく作っても意味がいのです。
6. 動画化でよくある失敗と、その回避法
ではここからは、教育動画のありがちな失敗例と、その対処法を紹介します。
① 長すぎる動画を作ってしまう
- NG:「15分の研修動画を1本だけ」
- OK:「3分×5本に分ける」「冒頭に目的を入れる」
② 内容が古いまま放置
- NG:3年前の手順を今もそのまま公開
- OK:定期的に見直す仕組み(更新日・レビュー担当者)
③ 一方的に見せるだけ
- NG:ただ再生して終わり
- OK:クイズ・感想提出・グループワークとの連動
動画は“万能ではない”けれど、正しく使えば最強の武器になります。
7. 実際に動画教育を導入した企業の声
✅中小製造業:
「熟練スタッフの“クセ”が動画で共有できた。マニュアルじゃ伝えきれなかった“手の角度”まで見せられる」
✅ IT企業:
「エンジニアの育成スピードが上がった。“誰に聞くか”で悩む時間が減った」
✅ 接客業:
「店舗によって教え方がバラバラだったのが統一された。“新人が使える人材になるまでの期間”が短くなった」
8. 教育動画の導入がもたらす本質的な価値
ここがこの記事のキモ。
教育動画の導入で得られるものは、単なる「効率化」だけじゃありません。
- 教育の属人化からの脱却
- 採用・育成の再現性UP
- 誰かが辞めても崩れない組織作り
- リモート・フレックスにも対応可能
- 育成コストの見える化
そう、「教育のインフラ化」が実現するんです。
“担当者のスキル”じゃなく“会社の仕組み”で育てる。
それができると、会社はグッと強くなります。
9. 動画教育は「今あるもので始められる」
「動画ってハードル高そう…」
よく言われます。
でも、大丈夫。
- スマホのカメラでもOK
- 無料のスライド+録音ツールで作れる
- 最初は“1テーマだけ”で十分
たとえば、
- 朝礼の進め方
- お客様への挨拶の仕方
- 受発注ソフトの使い方
こんな内容でも、1~2分で動画にできます。
あとは現時点で研修担当がいるなら、研修中を録画しておいて動画編集は外注してしまえばコストも抑えれてクオリティーが高い研修動画が作れます!
そのとき、動画編集者に外注する際には
- 研修動画の合間にミニクイズを挟みたい
- 録画した動画を数本に分けたい
など要望をまとめておきましょう。
とにかく“最初の1本”を作ることが、すべてのはじまりです。
10. まとめ:研修の未来は“担当者”ではなく“仕組み”が作る
「教育は人がやるもの」——確かにそうかもしれません。
でも、“人だけに頼る教育”には限界があるのです。
誰かが辞めたとき、何かが変わったとき、その都度ゼロからやり直すのは、もったいない。
教育動画を使えば、“いつでも・誰でも・同じように学べる”環境が手に入ります。
それは、新人だけでなく、教える側のストレスも大きく減らしてくれます。
動画は、一度作れば何度でも使える。
だからこそ、“会社の資産”になります。
もう「研修担当が辞めたらどうしよう」と慌てる必要はありません。
教育の力を、“人”から“仕組み”へ。
その第一歩として、教育動画をぜひ取り入れてみてください。
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
この研修の課題、テーマはアニメーション動画との相性抜群です。
視覚で伝える・ストーリーで理解させる・ナレーションで補完する、という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください。