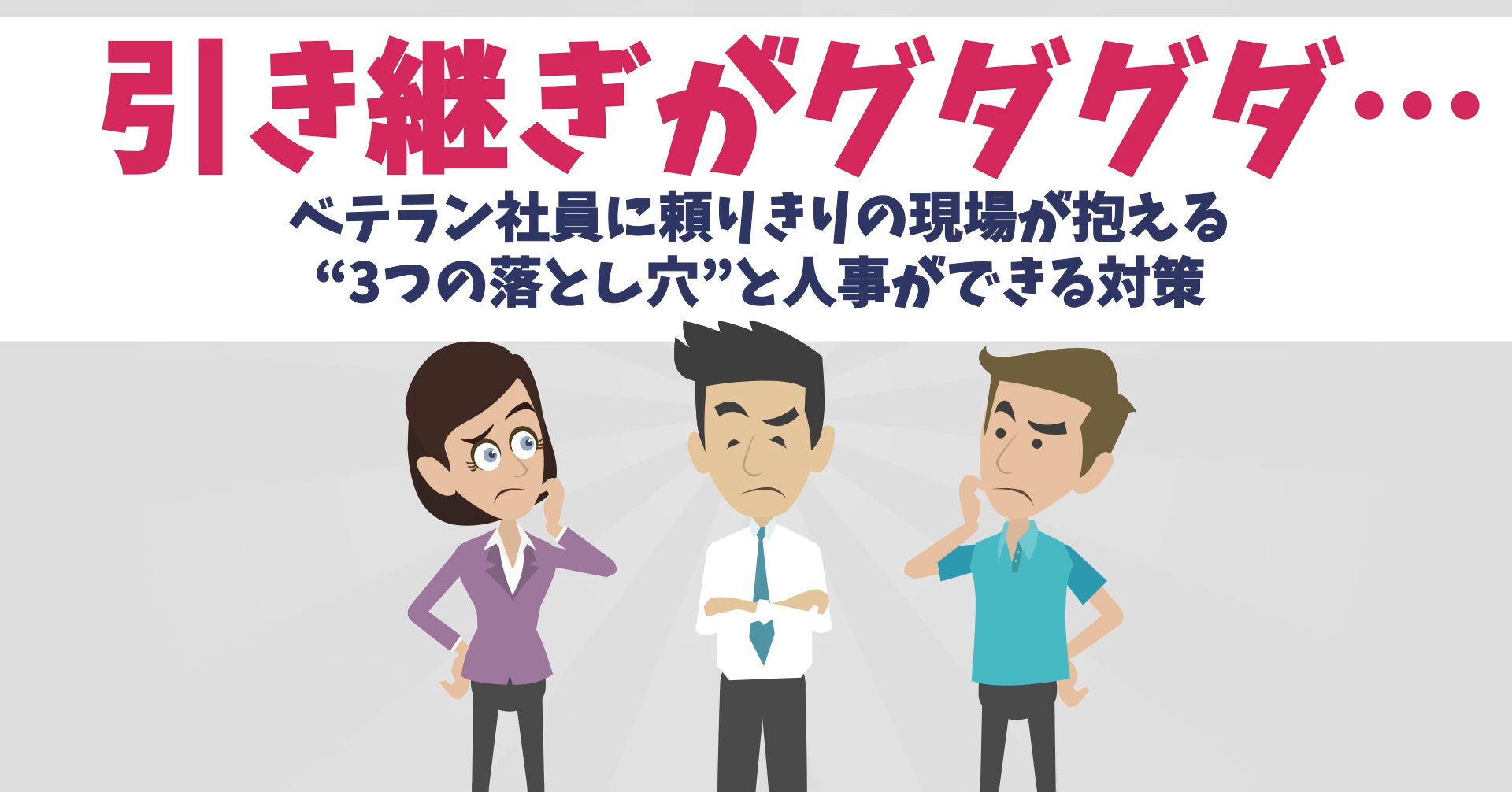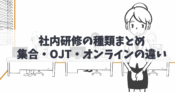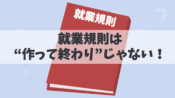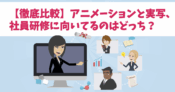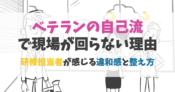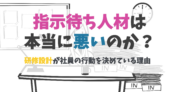【引き継ぎがグダグダ…】ベテラン社員に頼りきりの現場が抱える“3つの落とし穴”と人事ができる対策
結論:問題の根っこは「属人化」と「世代間ギャップ」。早めの仕組み化と相手本位の育成がカ
ベテラン社員の引き継ぎがうまくいかず、現場が混乱する。
クライアントから教育動画制作の際、こんなお悩みをよく聞きます。
- 急な退職で引き継ぎが間に合わない
- 何が重要かも曖昧なまま業務が進む
- 若手が聞いても「自分で考えて」と突き放される
こうした状況の背景には、業務の属人化と世代間のコミュニケーションギャップがあります。
この記事では、ベテラン社員の引き継ぎにありがちな3つの問題点を整理し、人事・経営層・現場リーダーが取るべき具体的な対策をご紹介します。
問題をイメージしやすいようリスト部分も詳細にお伝えします!
よくあるケース1:「急に辞める」と業務が回らない
引き継ぎは、余裕をもって丁寧に行うのが理想。
でも、現実はなかなかそうはいきません。
「もう少し時間があれば…」
「あと1週間早く言ってくれたら…」
そう思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
特にベテラン社員が急に辞めるケースでは、そのダメージは大きく、現場が一気に混乱することもあります。
時間がない中で引き継ぎが始まると、どうなる?
ある日突然、長年活躍してきたベテラン社員が「今月いっぱいで辞めたい」と申し出てきました。
そんな時、次のような問題が一気に噴出します。
- 業務が頭の中にしかない
- 後任が未定、または未経験者
- 引き継ぎ資料がないまま口頭で対応
当然ながら、引き継ぎは断片的になります。
時間も足りず、新人がメモを取りながら理解するしかなく、精度も再現性も低くなります。
原因は「業務の洗い出しがされていない」こと
ベテラン社員に限らず、人が長く業務を続けると、作業は“自動化”されていきます。
頭で考えずに体が動くようになり、それを改めて言語化するのは簡単ではありません。
さらに、その人しか知らない独自のやり方が積み重なることで、「他の人では再現できない属人化業務」が生まれてしまいます。
対策①:引き継ぎの「5ステップ」を仕組み化する
急な退職や異動でバタバタと始まる引き継ぎ。
でも実は、「誰が辞めても業務が回る仕組み」を普段から準備しておくことが、最も有効な対策になります。
とはいえ、
何から始めればいいの?
うちの会社でもできるの?
「何から始めればいいの?」「うちの会社でもできるの?」と悩む方も多いはず。
そこで、引き継ぎが属人化せず、スムーズに進むための5つのステップを整理しました。
この手順をもとに、あなたの会社でも今日から“仕組み化”を進めてみてください。
1. 業務の棚卸し
ベテラン社員にとっては毎日当たり前のようにやっている業務でも、それを初めて担当する後任者にとっては、すべてが未知の世界です。
たとえば——
取引先への月次報告書を作っておいて!
発注は在庫を見ながら適当に判断してるよ!
そんな一言で済まされがちな業務も、実際には“どの帳票を使うのか”“誰に確認するのか”“いつまでにやるのか”といった情報がなければ再現できません。
だからこそ、
この仕事は毎月15日締めで、○○部のAさんからデータをもらって、△△商事に提出してる
など、具体的な手順・タイミング・関係者まで一緒に書き出すことが重要なのです。
棚卸しをする際は、以下の視点も加えると、後任者が“流れ”をつかみやすくなります。
- どのくらいの頻度で行うか?(毎日/週1回/月末のみ など)
- 優先順位は高い業務か?急ぎでないものか?
- 誰と連携しているか?部署・担当者の名前まで明記
- 注意点や例外対応はあるか?
「これは言わなくても伝わるだろう」は禁物です。
後任者が“自分ひとりでもこなせる”レベルを目指して言語化していきましょう。
2. スケジュールの調整
「引き継ぎは○月○日からスタートして、週明けまでに○○業務まで終わらせよう」といったように、いつ・誰が・何を引き継ぐのかをスケジュールに落とし込むことが大切です。
たとえば、月末処理の担当者が退職する場合は、
「今週は請求書のチェック、来週は入金確認のやり方」
と段階的に分けて予定を立てます。
さらに、上司や関係部署にもその予定を共有しておくことで、
急に別の業務が入った。
後任が不在になった。
といった突発的な変更にも対応しやすくなります。
紙や口頭だけで済ませるのではなく、GoogleカレンダーやExcelなどで可視化しておくことがポイントです。
そうすることで、関係者全員が「今どの段階か」「次に何を引き継ぐのか」が一目で分かります。
4. 実地での引き継ぎ(OJT)
資料やマニュアルだけでは伝わらない、“その場でしか気づけない感覚”があります。
たとえば、ベテラン社員がよく言う、
この処理だけは例外だから、前もって△△課に声かけておいて
このファイルは○○さんが触るから、名前を変えないでね
といった注意点は、実際の業務の流れの中でないと伝わりづらいもの。
そこで有効なのが、OJT(On the Job Training)形式の引き継ぎです。
たとえば、ベテランと新人が並んでPCを操作しながら、
- 書類作成 → 提出のルート
- 他部署への確認の“ひと言”の入れ方
- 顧客対応のメールの文面の書き方
などを、作業しながら実演・実習する形で伝えると、記憶にも定着しやすくなります。
また、新人側がメモを取りやすいように、「次はこの作業をやるよ」と先に流れを示しておくと、OJTがよりスムーズになります。
OJTのポイント
- 作業しながら口頭で「なぜそうするか」を伝える
- 少しずつ操作を新人に任せてフィードバックする
- ミスしやすいポイントは実演しながら強調する
ただ見せるだけでなく、“体験させる”のがポイントです!
5. フォローアップ体制の確保
引き継ぎ完了後、最低でも1〜2週間は質問や確認ができる窓口やチャット環境を整えましょう。
「ここが分からなかった」と気軽に言える空気づくりが、引き継ぎ精度を高める鍵になります。
よくあるケース2:「ベテラン社員の指導がきつすぎる」問題
引き継ぎやOJTの場面で、もう一つ大きな壁になるのが
“教える側と教えられる側の温度差”です。
教えたのに、なぜ伝わってないんだ?
聞いたけど、よく分からなかった…
このすれ違いは、決して能力や意欲の問題ではなく、世代間のコミュニケーションスタイルの違いが影響しているケースがほとんどです。
特にベテラン社員が悪気なく取っている態度や言葉が、若手にとっては「怖い」「相談しづらい」空気をつくってしまうことも…。
そんな、“指導するつもりが逆効果になってしまう”場面を整理してみましょう。
若手が“言いたくても言えない”空気
引き継ぎはされたけど、よくわからないまま進んでいる
質問すると怒られそうで聞きづらい
こうした声が若手社員から挙がる背景には、ベテラン社員とのコミュニケーションの壁があります。
知識も経験もあるベテランほど、「なぜこれがわからないのか」が理解できず、無意識のうちに高圧的な態度になってしまうことがあります。
現場でありがちな“教え方のギャップ”
- 自分語りばかりで本題に入らない
- 話が長く、結論が見えにくい
- 「こんなことも分からないの?」という雰囲気
これでは、若手が自分から質問することが難しくなり、表面的に“分かったフリ”をしてしまうのです。
対策②:世代間ギャップを埋める「教え方の工夫」
引き継ぎは「教える側」の姿勢で、大きく成果が変わります。
とくにベテラン社員と若手社員の間には、育ってきた時代背景や価値観の違いがあるため、
同じ伝え方では通じない場面も多く見られます。
言わなくても分かるだろう
昔はこうやって覚えたものだ
そんな感覚は、いまの若手社員にはなかなか響きません。
かといって、全てを“優しく教えればいい”という話でもありません。
大切なのは、「どう伝えるか」にひと工夫を加えること。
ここでは、Z世代・ミレニアル世代といった“今どきの若手”にも伝わりやすい指導の工夫ポイントを具体的にご紹介します。
小分けに話す
一度に全てを詰め込まず、ひとつの作業が終わるたびに「ここまで大丈夫?」と区切りながら進めると、若手の理解度が上がります。
失敗談や裏話を交える
「この作業、昔ミスして怒られたことあるから気をつけてね」といったエピソードは、単なる注意喚起ではなく、聞き手の記憶に残りやすくなります。
相手の反応を見ながら調整する
「ちゃんと聞いてるかな?」ではなく、「伝わってるかな?」の視点で観察することで、適切なスピードや説明量に調整できます。
よくあるケース③:採用したベテランが“現場をかき乱す”\
中小企業では、経験豊富な人材を「即戦力になってくれるはず」という前提で採用するケースが多くあります。
ところが実際には、
スキルは高いのに、現場の空気がむしろ悪くなるというパターンも珍しくありません。
たとえば
- これまでの成功体験からプライドが高く、会社のルールを軽視する
- 若手に対して上から目線の態度をとる
- 社長や上司の方針より、自分の“やり方”を優先してしまう
こうした行動が重なると、周囲の士気が下がり、
結果的に チーム全体のパフォーマンスに悪影響 を及ぼしてしまうことがあります。
ポイントは、これはスキル不足ではなく、
価値観や働き方の“マインドのミスマッチ” から起こる問題だということ。
研究でも、組織のやり方や文化にフィットしない人(ミスフィット)は、
- 不満やストレスを抱えやすい
- ルール違反や自己流の行動に走りやすい
- 結果として周囲の協力関係が崩れる
という傾向が指摘されています。
つまり、いくら能力が高くても、その会社の文化・考え方・スタイルと噛み合わないと、
「即戦力どころか現場を乱す存在になる」ことは十分起こりうる のです。
だからこそベテラン採用では、経験だけでなく
価値観・協調性・チームとの相性を丁寧に見極めることが重要になります。
対策③:採用後の「段階的育成」と“見極め”が重要
最初は現場業務からスタート
いきなり責任あるポジションに任命するのではなく、まずは通常業務を経験させることで、社風や働き方の理解を促します。
業務ルールは明文化して伝える
「うちは報連相よりも先に共有」が基本といった“当たり前”も、言葉にしないと伝わりません。
小さな成功体験を積ませる
一つの仕事をうまくこなせたら、その都度認め、フィードバックを送ることで、プライドと自信を適度に育てることができます。
タイプ別に見るベテラン社員の見極め
| タイプ | 特徴 | 関わり方 |
|---|---|---|
| 短期離職型 | 合わないとすぐ辞める | 面談で早めに見極め、ダメージ最小化 |
| 遅咲き型 | 慣れるのに時間がかかるが実力あり | 長期的な育成計画を組む |
| 言い訳型 | うまくいかないことを他責にする | チームへの影響を考慮し、継続雇用を見直す |
まとめ:引き継ぎ・指導・採用のすべてに共通するもの
属人化された業務がグダグダの引き継ぎを生み、 ベテラン社員とのギャップが若手の離職を加速し、 安易な採用が組織の空気を壊してしまう——
これらはすべて、“準備と姿勢”の差で防げる問題です。
- 引き継ぎは、構造化と見える化で再現性を持たせる
- 指導は、相手の立場を想像しながら“伝わる工夫”を
- 採用後は、段階的に評価しながら信頼関係を築く
そして、特に中小企業では、社長の判断基準を言語化し、社内で共有することが最大の安定策となります。
今こそ「人に依存する組織」から、「誰でも働ける仕組みのある会社」へシフトしていきましょう!
研修内容を一度、整理してみませんか?
研修内容を整理するところから、一緒に考えるお手伝いもしています。
- 何を教えるか
- どこまでやるか
- どう進めるか
研修を考える中で、
ここが曖昧なまま進んでしまうケースはとても多いです。
その結果、
- 「伝えたつもりだった」
- 「現場で行動が変わらなかった」
という声もよく聞きます。
まずは、今の研修内容や悩みを言葉にして整理するところからで大丈夫です。
まだ具体的に決まっていなくても問題ありません。
この研修、どう組み立てればいいんだろう?
そう感じたタイミングが、見直しを始めるベストなタイミングです。
お気軽にご相談ください。