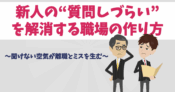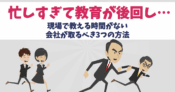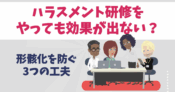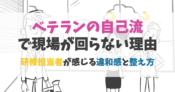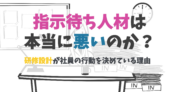『現場の声を活かせ』と言うけれど…なぜフィードバックが形にならないのか?
結論!!現場の声は“会社の未来”をつくる最重要資産!
現場には、顧客のリアルな声も、業務改善のヒントも眠っています。
にもかかわらず、「意見は大事」と言いつつ、実際には活かされない会社が多いのが現実です。
現場の声を“活かす会社”と“スルーする会社”の差は、やがて業績や社員の熱量に大きな差となって表れます。
この記事では、現場の声がなぜ活かされないのかを掘り下げ、今日から実践できる改善策をご紹介します。
現場の声は経営成功のカギ
現場には“宝の山”がある
- 売上に直結する顧客ニーズ
- 作業効率を上げるヒント
- 業務フローのムダ
現場は「顧客の声」と「業務のリアル」が集まる場所です。
つまり!情報は、会議室ではなく「現場」にこそ詰まっています。
現場の声を反映できる会社ほど成長し、市場での競争優位を築いています。
実際昔働いていた会社では、上が現場の声を無視して会議決めたことを実践しても何も変わることがなかったことがあります。。。
現場の声を反映できる会社ほど強くなる
トヨタでは歴代社長が“現地現物”を徹底!
実際に現場に足を運び、数多くの改善手法を生み出してきたことが、世界屈指の競争力に結びついています。
マネジメントの神様ドラッカーも「現場に行かなければ、なにもわからない」と説いています。
なぜ“現場の声”が活かされないのか?
「意見は言ってほしい」と言いながら、出てきた声をスルー
これは本当にあるある。。。
意見をまとめて伝えた意味とは。。。
よくある“スルーの構図”
- 意見箱は設置されているけど、誰も確認していない
- 会議で出た提案がその場で流される
- 上司に伝えたつもりが「あとで考える」と曖昧な反応
このような状況が続くと、社員は「どうせ言ってもムダ」「時間のムダ」と感じるようになります。
つまり“声が届かない”のではなく、“届いたけど何も起こらない”という経験が、現場を黙らせてしまうのです。
管理職の“機能不全”が現場を追い込む
「上に相談してもムダ」「変わらないから」「言う気も起きない」
「無理があったとは思わなかった」「問題に気づかなかった」
このように、現場と管理職の間には深い認識のズレがあります。
なぜ機能不全に陥ったのか?
リーマンショック後、企業はコストを削りながら世界との競争にも対応しなければならず、自然と
「業績目標の引き上げ」や「短期成果のプレッシャー」
が強まっていきました。
その結果、次のような事態が広がりました。
- 苛烈な上からの要求が現場に慢性的なストレスを与える
- 優秀な社員ほど離職、残った社員の疲弊が加速
- 経営陣は“原因”ではなく“症状”を是正しようとする
- 社員は「何もしない方が得」と沈黙を選ぶ
このような悪循環の末、社内には“あきらめ”と“無関心”が蔓延し、組織全体が機能不全に陥っていきます。
改善へのヒント
そんな空気が会社に広がってしまうのは、日本特有の“減点方式”の文化が原因かもしれません。
どうせ言ってもムダ・・・
ミスを責める文化では、意見もアイデアも生まれにくくなります。
いま東証では、上場企業にPBR(株価純資産倍率)1倍超えを求めています。
つまり、企業価値を高めなさい!!ということ。
それを実現するには、机上の戦略だけでなく「現場の声」をどう活かすかがカギになる時代です。
経営者こそ“現場の声”を聞くべき理由
現場を見ずに飛ばすフィードバックは、どこか他人事に聞こえてしまいます。
経営陣が現場を知らなければ、言葉の重みも信頼も生まれないのです。
同じ情報でも受け取り方・活かし方が異なる
業務量が多すぎます。。。
という社員の声。
それを「サボりたいだけ」と切り捨てるのか、
「そもそも仕事の設計にムリがあるのでは?」
向き合うのかで、会社の未来は全然違ってきます。
現場でしか得られない“気づき”がある
なんか違和感あるな。。。
そう思える感覚は、現場に足を運ばなければ得られません。
- フローのムダ
- 社員の疲れた顔
- なぜか止まる手元──。
数字やKPIだけでは見えてこない“変化のサイン”が、現場には詰まっています。
現場に足を運ぶことは“信頼のメッセージ”
上からの言葉より、そばにいる姿の方が信頼される。
経営陣が現場に来ることで、「ちゃんと見てくれてる」と思える。
だからこそ、社員も安心して声を上げられるんです。
働き方の多様化によるリスクへの配慮
リモートワークやシフト制など、働き方が多様化した今、社員と顔を合わせる機会は確実に減っています。
その結果、現場の本音や小さな声が経営陣に届きにくくなるリスクが高まっています。
この“声の空白”にどう向き合うか──。
経営者自身が意識を変える必要があります。
“現場の声”をスルーする会社の5つの盲点
- 意見箱の放置:書かれたまま誰も読まない、返信もない
- 会議でのスルー:勇気を出して言った声が無視され、モチベ低下
- 判断基準が不明確:どんな意見が採用されるのか分からない
- 経営層に届かない:現場→中間管理職で止まりがち
- 意見を出した人にフィードバックがない:結果が返ってこないと「言う意味がない」と感じる
これらが積み重なると、意見を出す文化そのものが崩れてしまいます。
現場こそが成功の源泉
マクドナルド創業者のレイ・クロックは、出店後も現場に足を運び、自らポテトを揚げていたと言われています。
イケアの創業者カンプラードも、商品棚の設置から顧客の動線までを自らチェックし、改善を繰り返しました。
“会社の成長も、衰退の兆しも、すべては現場にある”という考え方が、彼らを成功に導いた共通点です。
経営者は危機を感じたときこそ、現場の声に立ち返るべきです。
“意見が育つ”職場にするための3つの仕組み
① 意見の“可視化”と“ステータス管理”
- TrelloやNotion、Slackなどを活用して、「誰が・どんな声を・いつ上げたか」を記録
- ステータスを「対応中/保留/却下(理由つき)」で管理することで、納得感を持ってもらえる
② フィードバックループの構築
- 意見を採用・却下する際、理由を返すことが次の声につながる
- 「良い提案だったので、来月の全体会議で共有させてもらいます」など、称賛も含めて返す
③ 成果が出た改善案は“社内で共有”する
- うまくいった改善事例は「成功ストーリー」として展開し、他部署にも刺激を与える
- 動画でのストーリー紹介や社内掲示板の活用も効果的
働き方の多様化で「現場の声」が届きにくくなっている?
リモートワークやシフト勤務の増加により、社員と顔を合わせる機会は確実に減っています。
一見、SlackやTeamsといったチャットツールで「つながっている」ように見えても──
本音や違和感、ちょっとした不満は、意外と出てこないものです。
とくに、
- チャットでは雑談しにくい
- “空気”が読めないから本音が出しづらい
- 自分だけ違う意見を言うのが怖い
こうした理由から、「発信しない人の声」は埋もれてしまいがちです。
だからこそ今、「意見を集める仕組み」そのものを見直す時期にきています。
時代に合った“声の拾い方”へ、アップデートが必要です。
最後に:現場にこそ、答えがある
経営を成功へ導くには、経営者が「現場の声」に耳を傾け続ける姿勢が欠かせません。
机上の理論ではなく、リアルな課題も、気づきのヒントも、現場にあります。
業績が伸び悩んだとき、社員のモチベーションが下がっていると感じたとき、なにか社内にギクシャクした空気が流れているとき──。
そんなときこそ、まず立ち返るべきは「現場の声」です。
その声に耳を澄ませ、拾い上げ、活かせる組織こそ、変化の激しい時代でも勝ち残る企業となっていけるはずです。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました!
映像制作テンツキでは、
- クライアント用説明動画
- 新人社員マニュアルの動画化
- 研修動画の構成・企画・制作
などを行っています。
アニメで「視覚的にわかる」
ストーリーで「理解が深まる」
ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください!