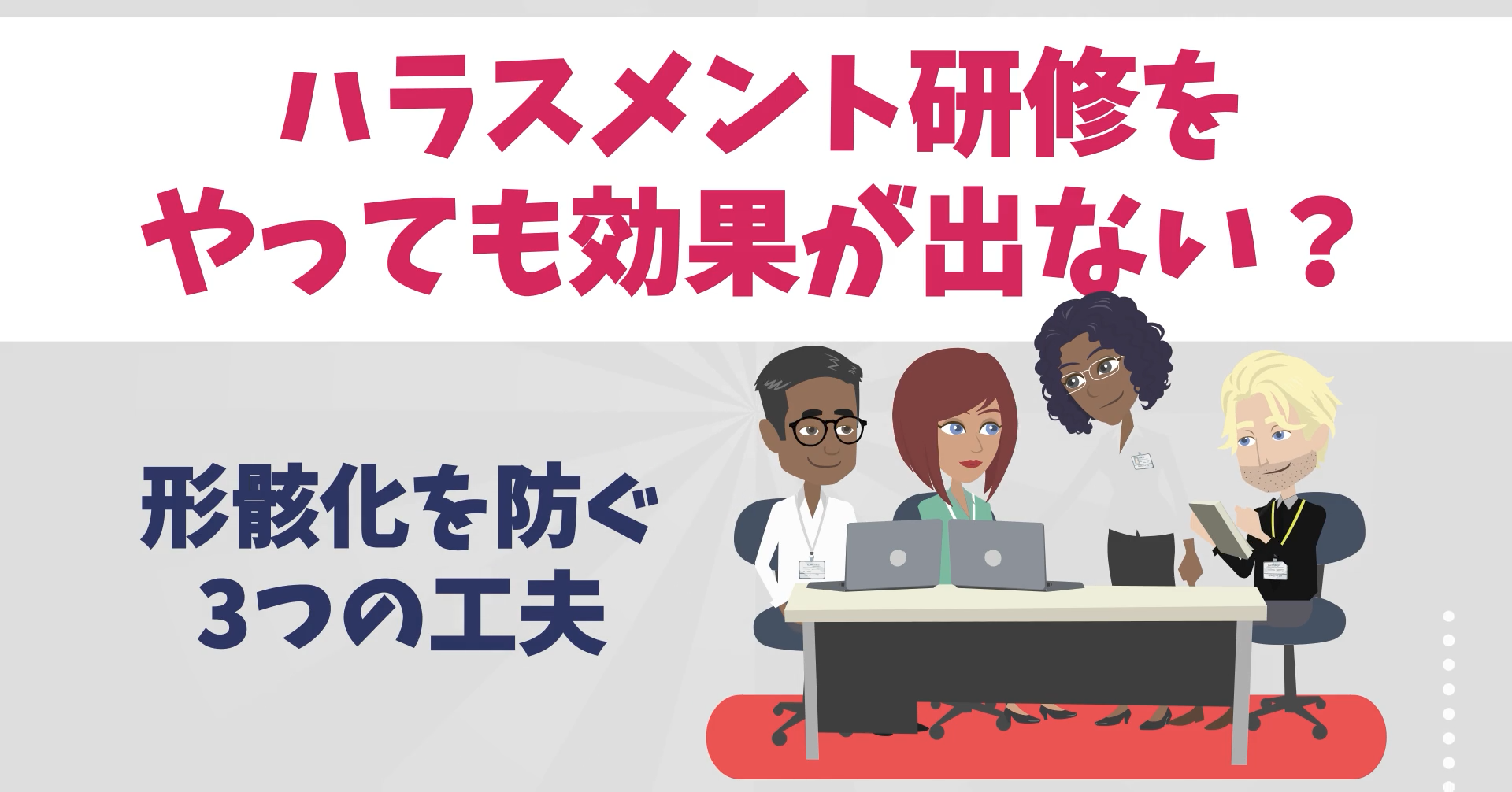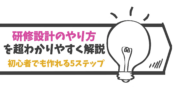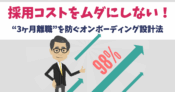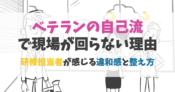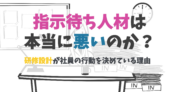ハラスメント研修をやっても効果が出ない?形骸化を防ぐ3つの工夫
結論:ハラスメント研修は「やっただけ」では意味がない
社労士として顧問先をサポートしていると、
ハラスメント研修はやったけど、正直あまり効果を感じない。。。
形式的に座学で受けただけで、その後は何も変わっていない。。。
そんな声をよく耳にしませんか?
法律でパワハラ防止措置が義務化され、ほとんどの会社が「とりあえず研修をやる」流れになっています。
しかし、実際には “受けました”という事実だけが残って、社員の意識や行動が変わらない ケースも多いのです。
本当に大切なのは、「やったこと」ではなく「その後どう変わったか」。
この記事では、ハラスメント研修が形骸化してしまう理由と、実効性を高めるために社労士が提案できる3つの工夫を解説します。
形骸化する研修のよくあるパターン

① 法律条文を読むだけの座学
よくあるのが、
- 「パワハラ防止法の条文」
- 「労働施策総合推進法のポイント」
をひたすら説明する研修。
もちろん法律の知識は大事ですが、社員からすると「聞いて終わり」で、実生活にどう関係するのかが見えづらいのです。
② 動画を流して終わり
Eラーニングや外部教材を流すだけで、感想も確認テストもなし。
見たけど内容は覚えてない
なんてことも少なくありません。
③ 管理職だけが対象で、現場が置き去り
管理職研修はやったけど、一般社員には何もしていない
これも非常によくあるケースです。
実際には、ハラスメントの加害者も被害者も、現場社員が大半。
管理職だけに伝えても、会社全体の空気が変わることはありません。
実効性を高める3つの工夫
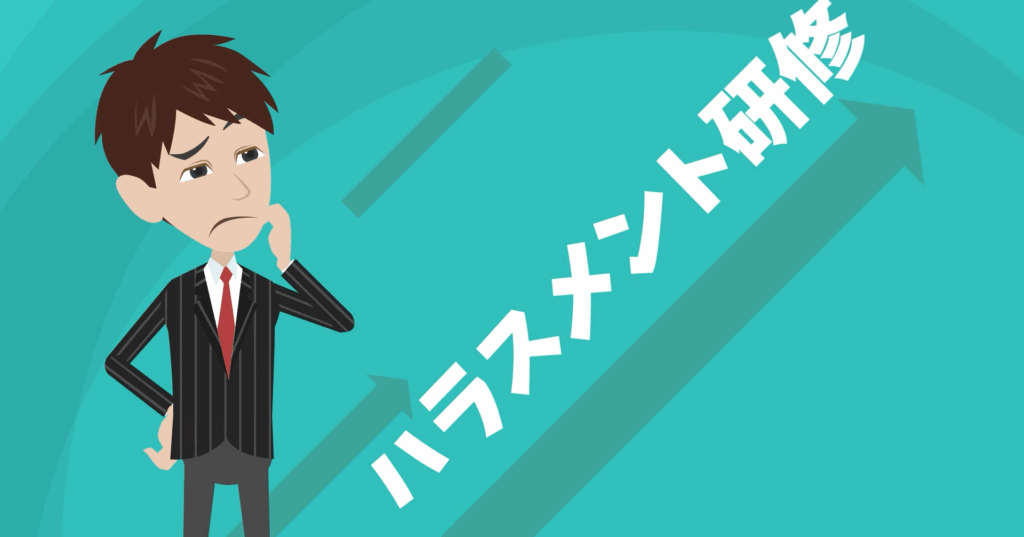
では、どうすれば「やった感」ではなく、本当に効果が出る研修になるのか。
ここからは、社労士が顧問先に提案できる3つの工夫をご紹介します。
工夫① ケーススタディで「自分ごと化」させる
人は、自分に関係ないと思ったことは行動に結びつきません。
だからこそ、研修では「よくある事例」をケーススタディにして、参加者自身に考えてもらうことが効果的です。
たとえば
- 「会議中に部下を大声で叱責するのはパワハラに当たる?」
- 「飲み会で『結婚しないの?』と何度も聞くのはどう?」
こうした具体的な事例を出してディスカッションすることで、
「自分の職場にもあるかも」「自分の言動もグレーかも」
と“自分ごと”として捉えやすくなります
工夫② ロールプレイで“対応の型”を体験する
「知識としてわかった」だけでは、実際の現場では行動できません。
だからこそ、ロールプレイで「対応の型」を体験させることが有効です。
- ハラスメントを受けた立場の人の対応
- ハラスメントを指摘された上司の対応
- ハラスメント相談を受けた人事担当の対応
こうしたシチュエーションを演じることで、参加者は「どう動けばいいか」を体で覚えることができます。
研修後も「型」として残るので、実務での再現性が高まります。
工夫③ 研修後に「振り返れる仕組み」を作る
一度きりの研修では、人はすぐに忘れてしまいます。
そのため、研修後に チェックリスト・動画・小冊子 など、振り返りツールを渡しておくことが重要です。
- 毎月のミーティングでチェックリストを使って確認
- 社内ポータルに3分のショート動画を置く
- 新人研修に同じ資料を組み込む
こうした仕組みを作れば、研修が「単発イベント」で終わらず、日常的に浸透していきます。
社労士が関わる意義
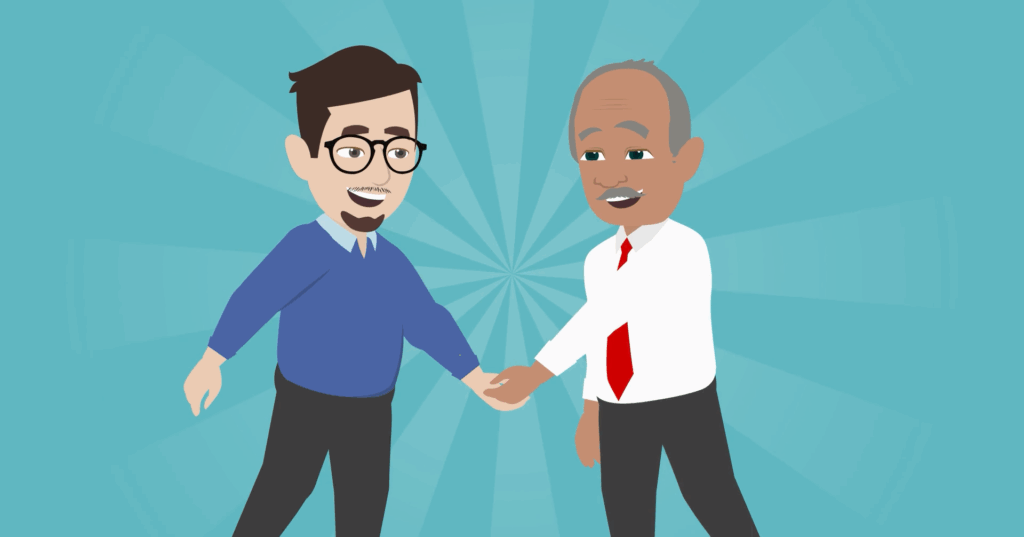
ここで「うちの会社でも工夫すればいいんじゃない?」と思われるかもしれません。
ですが、実際には現場だけで設計すると 「法律的に不十分」 だったり、逆に 「現場感覚とズレる」 ことが多いのです。
社労士が関わることで
- 法律に基づいた最低限のラインを守れる
- 現場の課題に寄り添った事例を組み込める
- 定期的なフォローアップの仕組みを提案できる
つまり「法律」と「実務」の両方をバランスよく押さえた研修を設計できるのです。
まとめ:形だけの研修から“実効性ある仕組み”へ
ハラスメント研修は「やったこと」そのものよりも、「その後に職場がどう変わったか」 が何より大事です。
- 法律の説明だけでは社員は動かない
- 動画を流すだけでは記憶に残らない
- 管理職だけでなく全社員が対象でなければ意味がない
だからこそ、
- ケーススタディで「自分ごと化」させる
- ロールプレイで「行動の型」を体験する
- 研修後も振り返れる仕組みを作る
この3つを押さえることで、研修は“形骸化”から“実効性ある仕組み”へと変わっていきます。
そしてその設計をサポートできるのが、社労士の大きな役割です。
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
などを行っています。
- アニメで「視覚的にわかる」
- ストーリーで「理解が深まる」
- ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
顧問先対応をもっと効率化したいと感じているなら、“動画で仕組み化”する第一歩を踏み出してみませんか?