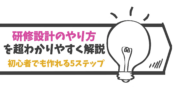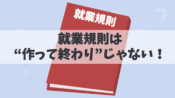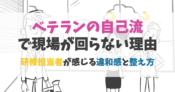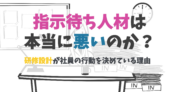採用コストをムダにしない!“3ヶ月離職”を防ぐオンボーディング設計法
結論:入社後3ヶ月の過ごし方が定着率を決める
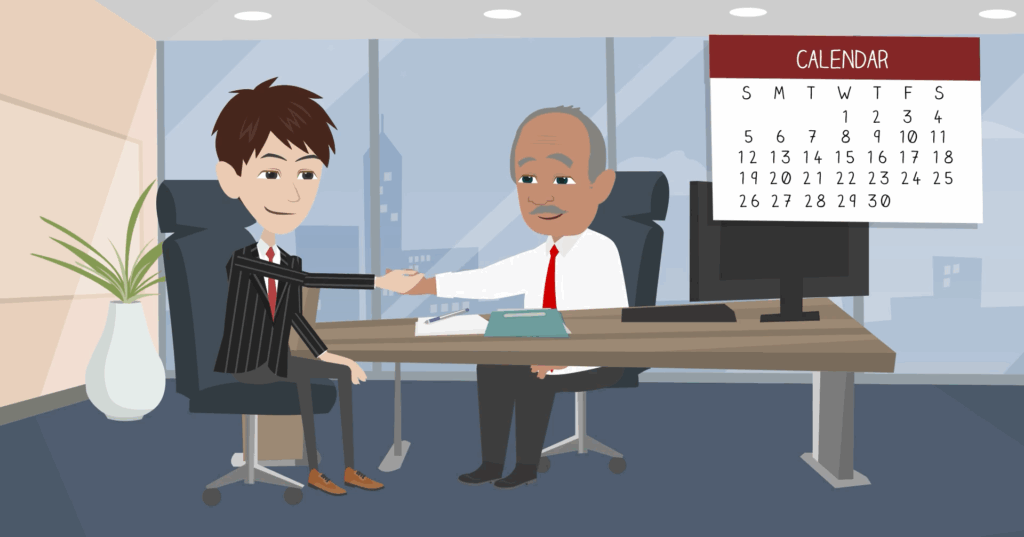
せっかく時間とお金をかけて採用した新人が、入社から数ヶ月で辞めてしまう。
この「3ヶ月離職」、実は多くの中小企業で起きています。
早期離職の原因は、スキル不足や給与だけではありません。
“入社後の受け入れ体制(オンボーディング)”の設計に問題がある場合がほとんどです。
- 初日に放置された
- 誰に相談していいかわからなかった
- 会社の雰囲気になじめなかった
こうした小さな不満や不安が積み重なり、
ここではやっていけないかも…
という気持ちに変わります。
だからこそ、入社後3ヶ月のサポートが定着率アップのカギになるのです。
1. 3ヶ月離職の現状と企業へのダメージ
意外と多い「数ヶ月で辞める」ケース
入社してまだ数ヶ月──。
ようやく名前や顔を覚えてきた頃に「辞めます!」と告げられる。
経営者や人事担当にとっては、これほどガッカリする瞬間はありません。
厚生労働省の統計でも、新卒だけでなく中途採用でも、半年以内に退職する人は珍しくないことがわかっています。
特に中小企業では、人員に余裕がないぶん、この“短期離職”はダメージが大きいのです。
採用コストは想像以上に重い
採用活動には、目に見える費用だけでなく、目に見えない時間コストもかかっています。
たとえば──
- 求人広告費や人材紹介料
求人サイト掲載や紹介会社への成功報酬など - 面接・採用担当者の時間
面接準備や調整、複数回の面談 - 入社後の教育・OJT
マニュアル作成や研修準備 - 先輩社員のサポート時間
本来の業務を一時的に減らして指導にあたる
これらを合計すると、1人あたり50万〜100万円以上になるケースは珍しくありません。
そして、もし入社から3ヶ月で辞められてしまったら…。
その投資はほぼ回収できないまま消えてしまいます。
さらに現場は再び人手不足になり、「また採用しないと…」という悪循環が始まります。
短期離職は、単に人が減るだけでなく、採用・育成のエネルギーそのものを失わせる厄介な問題なのです。
2. なぜ3ヶ月で辞めてしまうのか?主な理由
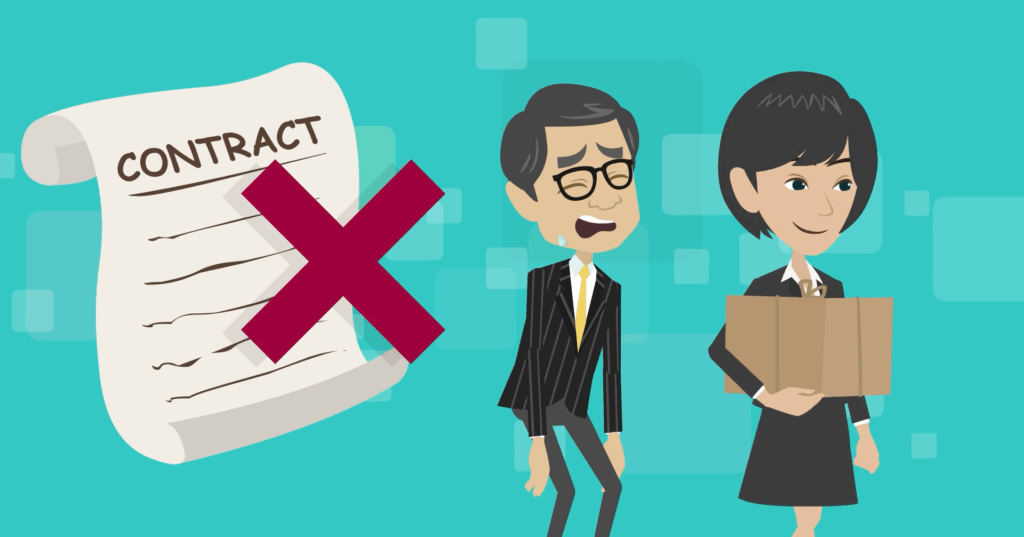
入社からわずか3ヶ月。
仕事にも少しずつ慣れ始めた頃に
すみません、辞めたいです…
と言われると、会社側は大きな衝撃を受けます。
では、なぜそんなに早く退職を決断してしまうのでしょうか?
理由は大きく分けて3つあります。
① 仕事内容のギャップ
- 「聞いていた仕事と違う」
面接では営業と聞いていたのに、実際はほとんどデスクワークだった。
あるいはその逆で、想像以上に外回りや体力仕事が多かった。 - 単調すぎる/責任が重すぎる
ルーティンばかりで飽きてしまうケースもあれば、いきなり大きな案件を任されてプレッシャーで押しつぶされそうになるケースも。
この“仕事内容のミスマッチ”は、短期離職の原因として非常に多いです。
特に中小企業では、採用時に全ての業務内容を細かく説明しきれず、「こんなはずじゃなかった」と感じさせてしまうことがあります。
② 人間関係の不安
- 上司や同僚と会話が少ない
挨拶はするけれど、業務以外の会話がほとんどない。 - 質問できる人がいない
「誰に聞けばいいのか」がわからず、悩みを抱え込んでしまう。 - 職場の雰囲気になじめない
長くいる社員同士の仲が良すぎて、新人が入り込む余地がない場合も。
人間関係の問題は、業務そのものよりも退職の決断を早めます。
「ここに居場所がない」と感じた瞬間、人は残る理由を見失ってしまうのです。
③ 将来への不安
- 成長のイメージが描けない
このまま働いてもスキルが身につく気がしない。 - 評価基準が不明
何を頑張れば評価されるのか、まったく見えない。 - 役割がわからない
チームの中で自分がどんな価値を発揮できるのかが曖昧。
こうした「先が見えない状態」は、意欲を急速に下げます。
特に若手社員は、未来のキャリア像がはっきりしない職場ではモチベーションを保つのが難しいのです。
共通点は「入社後のフォロー不足」
これら3つの理由は、突き詰めれば「入社してからのフォローが足りない」という共通点に行き着きます。
初期の段階でギャップや不安を解消する機会を作れれば、多くの早期離職は防げる可能性があります。
3. オンボーディングとは?基本の考え方
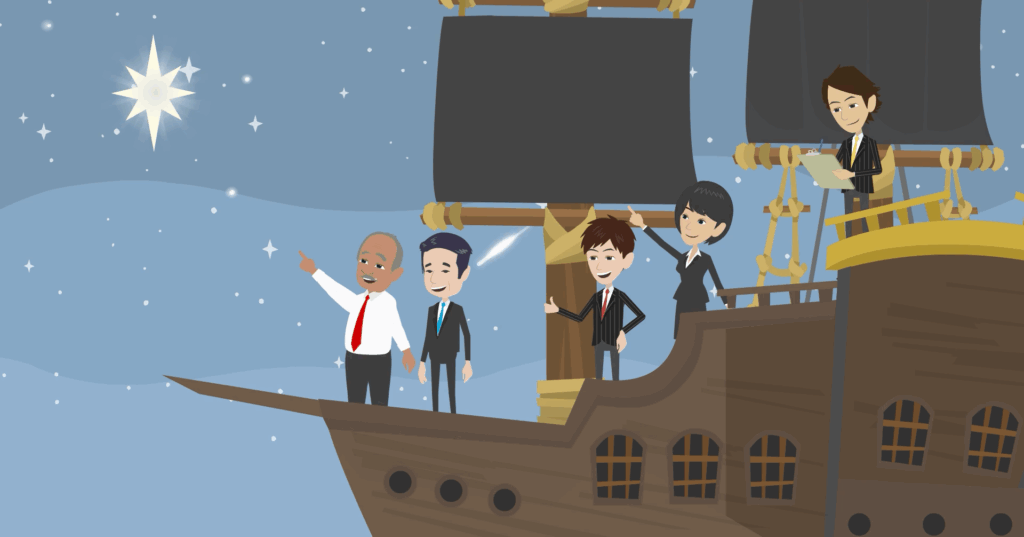
「オンボーディング(Onboarding)」という言葉は、もともと船に乗る(on board)という意味から来ています。
転じて、ビジネスの場では新しく入った人が、組織やチームにスムーズになじみ、戦力として活躍できるようになるまでの仕組みやプロセスを指します。
海外では常識、日本ではまだこれから
海外の企業では、オンボーディングは「人材を定着させるための当たり前の戦略」として定着しています。
たとえばアメリカの企業では、入社から数週間〜数ヶ月かけて、業務スキルだけでなく、会社の文化や価値観、仲間との関係づくりまで計画的にサポートします。
一方、日本ではまだ「新人研修」と混同されることが多く、研修さえやれば受け入れは完了という考えが根強く残っています
しかし実際には、研修はオンボーディングの一部に過ぎませ!
ポイントは「研修だけじゃない」こと
オンボーディングの本質は、単に業務マニュアルを教えることではありません。
大切なのは、日々の関係づくりと仕事への慣れを両立させることです。
- 業務スキルの習得
仕事のやり方を理解し、自分でこなせるようになる - 人間関係の構築
困ったときに頼れる相手がいる状態をつくる - 会社文化の理解
「この会社はこういう価値観で動いているんだ」と納得できる
これらが揃って初めて、新人は安心して力を発揮できるようになります。
なぜオンボーディングが重要なのか?
採用した人が早期に辞めてしまう背景には、「居場所のなさ」や「先が見えない不安」があります。
オンボーディングは、そうした不安を解消し、
この会社で頑張ってみよう!
と思える土台を作るためのものです。
つまり、オンボーディングは“離職防止の特効薬”であり、採用コストを守るための保険でもあるのです。
4. “初日”から3ヶ月までの実践ステップ

ここからは、3ヶ月離職を防ぐためのオンボーディング設計を、時系列に沿って具体的に紹介します。
ポイントは「タイミングごとに目的を明確にし、相手の心理に寄り添った対応をする」ことです。
ステップ1:初日の信頼づくり(Day 1)
初日は、新人にとって「この会社でやっていけるかどうか」を直感的に判断する重要な日。
ここでの印象が良ければ、その後の学びや挑戦にも前向きになれます。
やるべきこと
- 初日に放置しない
「とりあえずこの席で待ってて」はNG。最初の数時間は必ず誰かがそばについてサポート。 - デスクや備品を事前に準備
PC・名札・文房具など、初日から業務に入れる環境を整えておく。 - 歓迎のランチやミーティングを設定
業務の説明だけでなく、雑談や人となりを知る場を用意。
ポイント
初日のゴールは「ここに来てよかった」と思ってもらうこと。
業務スキルの習得よりも、心理的な安心感の確保が最優先です。
ステップ2:最初の1週間(Week 1)
最初の1週間は、新人が「この職場のリズム」に慣れる期間です。
不安と緊張が続く中でも、小さな成功体験を積ませることで自信をつけさせます。
やるべきこと
- 業務内容を小分けにして教える
一度に詰め込むと混乱するため、1タスクずつ段階的に説明。 - 質問しやすい雰囲気を作る
「何かあったら言ってね」ではなく、「ここまではどうだった?」とこちらから聞く。 - 1日の終わりに声をかける
「今日はどうだった?」の一言が、不安解消と関係構築につながります。
ポイント
この時期は「何がわからないのかもわからない状態」。
焦らせず、小さな達成感を毎日積み上げることがカギです。
ステップ3:1〜3ヶ月目(Month 1〜3)
この期間は、新人がある程度業務をこなしつつ、自分の役割や存在意義を実感し始める時期。
同時に、ここで孤立感や不安が高まると離職の危険信号になります。
やるべきこと
- 定期的な1on1面談(週1〜隔週)
進捗だけでなく、困っていることやキャリアの希望をヒアリング。 - 気持ちの変化を確認
「最近どう?」の軽い会話でメンタル面を把握。 - 評価基準やキャリアパスを説明
目標が見えると、やる気と安心感が格段に上がります。
ポイント
この時期のゴールは**「あなたはちゃんと見てもらえている」という安心感**を与えること。
その感覚があるだけで、離職率は大きく下がります。
補足:ステップごとに必要な視点
- Day 1 → 感情面の安心感
- Week 1 → 習慣化と小さな成功体験
- Month 1〜3 → 役割意識と未来像の明確化
オンボーディングは、この流れを意識することで初めて効果を発揮します!
5. 定着率が上がる会社の共通点

社員が長く働き続ける会社には、やはり理由があります。
業種や規模にかかわらず、定着率が高い企業には共通する仕組みや考え方が存在します。
ここでは、特に効果が高い3つのポイントを紹介します。
① 情報共有がオープン
- 業務マニュアルや社内ルールが見える化されている
社内の知識やルールが、一部の人だけの頭の中にある状態は危険です。
「聞かないとわからない」仕組みは、新人にとって大きなストレスになります。
定着率の高い会社は、マニュアルや手順書、過去の事例などを誰でもアクセスできる形で共有しています。
例:
- 社内ポータルサイトやクラウドでマニュアルを一元管理
- チャットツールのFAQチャンネルで質問と回答をストック
② 関係づくりを重視
- 部署をまたいだ交流機会がある
業務の枠を超えた人間関係は、仕事のしやすさや相談のしやすさにつながります。
定着率の高い会社は、部署横断のミーティングやランチ会、勉強会など、“つながり”を作る仕掛けを意識的に取り入れています。
例:
- 月1回の全社ランチ会
- 部署ごとの「お互いの仕事紹介会」
- オンライン雑談ルームの常設
③ 評価とフィードバックが明確
- 「何を頑張れば評価されるか」がわかる
ゴールが曖昧なまま走らされると、やりがいや達成感が得られず、早期離職の原因になります。
定着率の高い会社は、成果だけでなく、プロセスや努力も評価の対象にしており、「評価基準を見える化」しています。
例:
- 四半期ごとの面談で成果と課題を振り返り
- 期待している役割や目標を明文化
- フィードバックは“その場”で短く、こまめに行う
まとめ:採用は入社日で終わりじゃない
採用は、入社日がゴールではありません。
むしろそこからが本当のスタートです。
せっかく時間とお金をかけて採用した人材も、受け入れの仕組みが整っていなければ、数ヶ月で辞めてしまう可能性があります。
逆に、入社後の3ヶ月間を丁寧にサポートできれば、採用コストの回収はもちろん、社員の成長スピードや貢献度も大きく変わります。
成功のポイントは3つ
- 初日から3ヶ月のフォローが勝負
最初の印象とサポート体制が、その後の定着率を左右します。 - 関係づくりと成長イメージの提示が鍵
居場所があり、未来が描ける職場は、人を長く引きつけます。 - 定期面談と小さな成功体験で自信をつける
「自分はここでやっていける」という確信を持たせることが重要です。
意図的に作る「続けたい職場」
定着率の高い職場は、偶然できあがるものではありません。
日々のコミュニケーションや仕組みの改善を積み重ねることで、「長く働きたい」と思ってもらえる環境は意図的に作れるのです。
採用のゴールを「人を入れること」から「人が育ち、活躍し続けること」へ──。
その意識の転換が、企業の未来を左右します。のです!
関連記事
おわりに
などを行っています。
アニメで「視覚的にわかる」
ストーリーで「理解が深まる」
ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください!