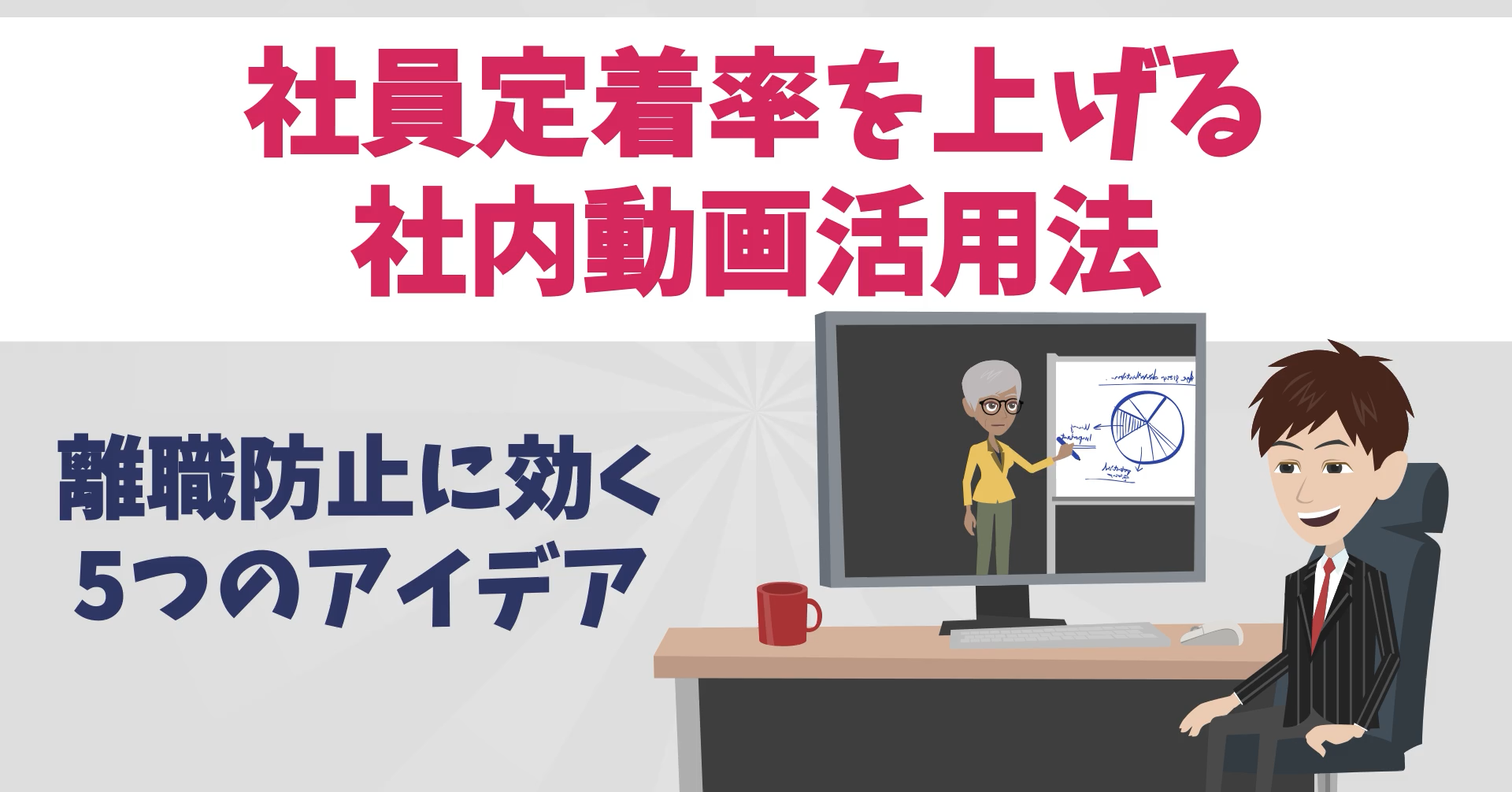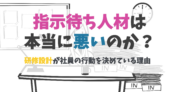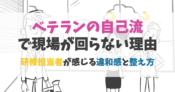社員定着率を上げる社内動画活用法|離職防止に効く5つのアイデア
結論:社内動画は「情報共有」だけじゃない。社員のつながりを強くする武器

多くの企業では、動画といえば研修用や採用PR用を思い浮かべるかもしれません。
もちろんそれらも重要ですが、「社内限定動画」にはもう一つの大きな役割があります。
それは──社員同士のつながりを強くし、会社への愛着を育てることです。
- 社長や上司からの想いを直接伝える
- 部署間で成功事例を共有する
- 新人が会社の雰囲気を知る
これらを映像で行うことで、離職率低下や社員定着率向上に直結します。
文章や口頭説明では伝わらない温度感や表情、声の抑揚が…
動画ならそのまま届くのです!
なぜ社員定着率が下がるのか?現場で起きている3つの変化
社内動画の価値を正しく理解するためには、まず「なぜ社員定着率が下がってしまうのか」を押さえることが大切です。
ここ数年、企業の働き方や職場環境は大きく変化しました。
その変化が、社員同士のつながりを弱め、結果的に離職防止を難しくしているのです。
主な背景は次の3つです!
(1) 働き方の多様化で顔を合わせる機会が減った
リモートワーク、時差出勤、シフト勤務…。
多様な働き方はワークライフバランスの向上に寄与する一方で、以前は毎日のように顔を合わせていた同僚と、物理的に会えなくなっています。
その結果、
- 休憩時間や出社前後の「雑談」がなくなった
- ちょっとした相談やアドバイスの機会が減った
- お互いの近況や人柄を知るきっかけが少ない
こうした小さな接点の減少は、知らないうちに社員同士の関係性を希薄にします。
仕事上のやり取りだけでは感情の交流が生まれにくく、「この会社で働く意味」を感じにくくなるのです。
(2) 部署間の距離感が広がっている
近年、業務はますます専門化・分業化しています。
そのため
自分の部署のことは分かるけれど、隣の部署が何をしているのか全く知らない。
という社員が増えています。
この状態では、
- 協力依頼や情報共有のタイミングがつかめない
- 他部署への感謝や尊敬の気持ちが芽生えにくい
- 会社全体の目標より、自分の部署の仕事だけに意識が偏る
結果として、部署間での心理的な壁が高くなり、社内の一体感が失われていきます。
これもまた、社員定着率の低下につながる要因の一つです。
(3) 新人が会社の雰囲気をつかめない
特にZ世代の新人社員は、SNSやオンラインでのコミュニケーションには慣れていますが、リアルな場での人間関係づくりには不安を抱くことがあります。
入社しても
- 誰に声をかけていいか分からない
- 先輩や上司の人柄がつかめない
- 会社の雰囲気や文化が見えない
こうした状況が続くと、せっかく入社しても職場に馴染む前に孤立感が強まり、早期離職へとつながってしまいます。
こうした問題に対し、社内動画は顔を合わせられない環境でも“人となり”や“会社の空気感”を共有できる有効な手段です。
物理的な距離や働き方の違いを超えて、感情や文化まで届けられる
これが社内動画の強みです!
社内動画が離職防止に効く理由

では、なぜ社内動画が社員定着率アップや離職防止に直結するのでしょうか?
理由は大きく3つあります。どれも「文章や口頭だけでは再現できない」動画ならではの強みです。
① 経営陣の想いが直接届く
メールや社内報などの文章は便利ですが、そこには“温度感”がありません。
同じメッセージでも、顔の表情、声の抑揚、間の取り方など、感情を伴った伝え方は文字では再現できないのです。
社内動画なら、経営陣が社員一人ひとりに語りかけるような臨場感を持って、
- ビジョンや経営方針
- これから挑戦したいこと
- 社員への感謝の気持ち
をダイレクトに届けられます。
この「直接会って話しているような感覚」が、社員の共感や信頼感を高め、結果的に定着率の向上につながります。
② 成功事例や努力が全社に共有される
現場では日々、小さな成功や改善が積み重なっています。
しかし、それらは同じ部署の中でしか知られず、他部署には届かないまま消えてしまうことが多いです。
社内動画を使えば、
- 顧客からの感謝の声
- チームが工夫して乗り越えたエピソード
- 数字だけでは見えない現場の努力
を映像として全社員に届けられます。
他部署の頑張りや成果を知ることで「自分たちも負けていられない」というモチベーションが高まり、会社全体の一体感が強まります。
③ 人柄や文化が可視化される
特に新人や異動してきた社員にとって、職場の雰囲気や同僚の人柄を知ることは安心感につながります。
社員紹介やインタビュー動画では、仕事の内容だけでなく、
- 趣味や休日の過ごし方
- これまでのキャリアや意外なエピソード
- チームの空気感や価値観
といった“人間らしい部分”を知ることができます。
こうした情報は、会話のきっかけや親近感を生み、職場への馴染みやすさを大きく高めます。
この3つの効果が組み合わさることで、社内動画は単なる情報伝達ツールではなく、社員のつながりや会社への愛着を深める「文化の媒体」として機能します。
これこそが、社内動画が離職防止に効く最大の理由です。
離職防止に効く!社内動画活用5つのアイデア
ここからは、実際に離職防止と社員定着率アップにつながる社内動画の活用アイデアを5つ紹介します。
いずれも導入のハードルが低く、すぐに始められる方法です。
1. 月1回の「社内ニュース動画」
毎月の成果や表彰者、プロジェクトの進捗などを3〜5分程度にまとめて配信する動画です。
例えば、営業部の契約達成報告や、製造部の品質改善事例などを短く紹介します。
効果
- 全社員が会社全体の動きを把握できる
- 他部署の頑張りを知ることでモチベーションが上がる
- 社員同士がコメントや会話を交わすきっかけになる
社内ニュース動画は、単なる情報共有ではなく、会社全体の一体感を醸成する仕掛けとして機能します。
2. 新入社員紹介ムービー
新入社員の趣味や特技、これまでの経歴などをインタビュー形式で紹介する動画です。
部署や拠点が離れていても、動画を通じて新しい仲間を知ることができます。
効果
- 先輩社員が声をかけやすくなり、新人の孤立を防げる
- 「どんな人が入ったのか」を全員が同時に知れる
- 新人本人も自己開示のきっかけを得られる
特に、リモートやシフト勤務で直接会う機会が少ない企業には効果的です。
3. 感謝・応援メッセージ動画
年末年始や繁忙期前などの節目に、経営陣や上司から感謝の言葉や激励メッセージを届ける動画です。
拠点が複数ある企業やリモート中心の職場でも、全社員が同じメッセージを受け取れます。
効果
- 社員のモチベーション維持
- 「自分の努力が認められている」という心理的安心感
- 会社全体での一体感の向上
文章やメールよりも、動画の方が感情や熱意がダイレクトに伝わります。
4. プロジェクト裏側ドキュメント
大きなプロジェクトやキャンペーンの成功までの過程を映像化した動画です。
関わったメンバーのインタビューや現場の様子を盛り込み、単なる結果報告ではなく「ストーリー」として共有します。
効果
- チームの努力や工夫が伝わり、感動や共感が生まれる
- 成功要因やノウハウを全社で共有できる
- 次のプロジェクトへの意欲が高まる
裏側を見せることで、成功の価値や意味が社員全員に広がります。
5. 社員スキル共有動画
社員が持つ専門知識や技術、業務のコツを短くまとめた動画を作り、社内で共有します。
例えば、接客のコツ、業務システムの使い方、営業トークの工夫など。
効果
- 教育コストを大幅に削減できる
- 社員間でナレッジが蓄積され、属人化を防ぐ
- 新人だけでなくベテランも学び直しが可能
知識が動画として残るため、「聞くタイミングを逃した」という状況を防げます。
この5つの方法は、いずれも「情報」と「感情」を同時に届けられる点で、離職防止と社員定着率向上に直結します。
まずは1つから試し、効果を実感したら段階的に拡大していくのがおすすめです。
導入事例
導入事例は以下になります!
事例① IT企業A社
課題:部署間の交流不足とリモート社員の孤立感
施策:月1回の社内ニュース動画を配信
効果:コメント機能で部署間の会話が増え、離職率の減少
事例② 製造業B社
課題:新人が現場の雰囲気に馴染めず、定着率が低い
施策:新入社員紹介ムービーと現場紹介動画を配信
効果:新人と先輩の交流が増え、定着率の向上
社内動画活用を成功させる3つのポイント
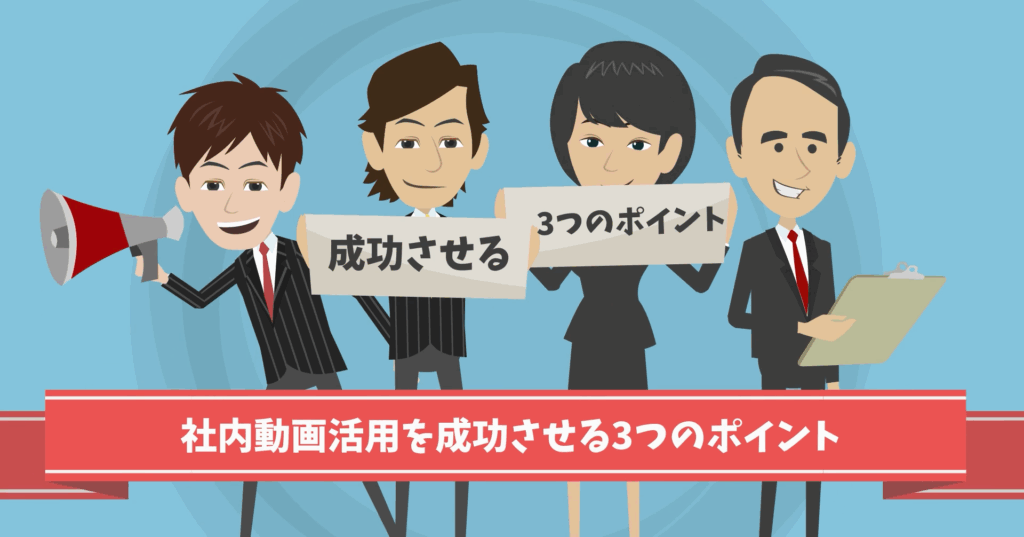
社内動画は作るだけでは効果が出ません。
社員定着率アップや離職防止につなげるためには、見てもらい、活用され続ける仕組みが必要です。
ここでは、導入後に成果を最大化するための3つのポイントを紹介します。
1. 短くテンポよく
社内動画は、3〜5分程度がベストです。
それ以上長くなると、途中で視聴をやめてしまう社員が増え、せっかくの内容が最後まで届きません。
- 理由:業務の合間に見られる長さが理想
- コツ:要点を絞り、映像・テロップ・音声をテンポよく切り替える
例えば社内ニュース動画なら、「成果紹介→表彰→プロジェクト進捗」のように3パートに分け、それぞれ1分以内でまとめると最後まで視聴されやすくなります。
2. 更新を継続する仕組みづくり
社内動画の効果は、一度作っただけでは発揮されません。
継続的に更新することで、「また見たい」という習慣が社員の中に生まれます。
- 頻度の目安:月1回、または四半期ごと
- ルール化:配信日を固定し、担当者や制作フローを明確にする
- ポイント:内容のバリエーションを持たせ、飽きさせない
更新が途絶えると、「あの動画はもう終わったのかな?」と関心が薄れ、定着率アップの効果も減少します。
3. 視聴環境を整える
どんなに良い動画を作っても、「見たいときに見られない」環境では意味がありません。
社員が手間なくアクセスできる仕組みを整えることが大切です。
- 方法例:社内ポータル、共有ドライブ、社内SNS(SlackやTeams)
- 工夫:スマホやタブレットでも視聴可能にする、動画の検索機能を用意する
- 効果:拠点や勤務形態を問わず、全社員が均等に情報を受け取れる
特にリモートワークや複数拠点を持つ企業では、この視聴環境整備が動画活用成功のカギになります。
7. まとめ:社内動画は「文化のインフラ」
給料や福利厚生の改善はもちろん大切です。
しかし、それだけでは社員定着率を本当の意味で上げることはできません。
長く働きたいと思える職場には、「会社への愛着」と「人とのつながり」が欠かせないのです。
そのためには、日常の中で「自分はこの組織の一員だ」と感じられる瞬間を増やす必要があります。
社内動画は、単なる情報共有の手段ではなく、会社の文化や経営陣の想い、仲間同士の絆を全員に同じ温度で届けるツールです。
表情や声の抑揚、現場の雰囲気までを映像として共有できるからこそ、文章や口頭では届かない感情が伝わります。
そして重要なのは、完璧な仕上がりを目指して始めるのではなく、小さくてもまず始めてみること。
例えば、スマホで撮った社長の1分間メッセージや、部署のちょっとした成果報告動画からでも構いません。
それがきっかけとなり、社内の空気は少しずつ変わっていきます。
離職防止やエンゲージメント向上を本気で目指す企業にとって、社内動画はこれからの時代に欠かせない“文化のインフラ”です。
今日から、あなたの会社でも一歩を踏み出してみませんか?