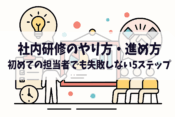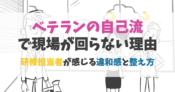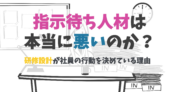「うちの若手、指示がないと動けない…」と悩むあなたへ。指示待ち社員が生まれる理由と上司の関わり方
結論:指示待ち社員は“性格”の問題ではない
最近の若手は、指示がないと全然動けない…
そんな声をクライアントやSNSなどでもよく聞きます。
けれど、その現象を「最近の若者は受け身だ」と片付けてしまうのはもったいない話かもしれません!
実は、指示待ち社員が生まれる背景には、
- 本人の性格
- 教育
- 社会
- 職場環境
- 上司の関わり方
このようにさまざまな要因が複雑に絡んでいます。
つまり、環境を整え、接し方を少し変えるだけで、彼らは“自分で考えて動ける社員”に育っていく可能性を持っています。
この記事では、指示待ち社員の特徴や心理、組織が抱える要因、そして上司や人事部門にできる具体的なアプローチを紹介していきます。
指示待ち社員とは?なぜいま問題視されるのか
「指示待ち社員」とは、指示がなければ動けない社員のこと。
何かしら行動するにも
これやってもいいですか?
次どうすればいいですか?
と確認をとらないと動けないタイプです。
一昔前までは「言われたことをしっかりやる」ことが評価されていました。
しかし今は、変化のスピードが速く、マニュアルに書いていない場面にも自ら考えて行動する力が求められています。
このギャップが、現場リーダーや上司のモヤモヤにつながっているのです。
指示待ち社員の心理は主に3タイプ
1. 目標欠如型
将来のキャリアビジョンが描けておらず、「とりあえず働いている」感覚のタイプ。やらされ感が強く、自主的に動こうという意識が湧きにくい。
2. リスク回避型
過去の失敗体験や強い叱責がトラウマになっていて、「また怒られるかも」という不安から自分の判断で動けなくなっているタイプ。
3. 自己肯定感欠如型
「自分なんかがやっても…」と自信を持てないまま行動を止めてしまうタイプ。
チャレンジよりも現状維持を選びやすい。
社内にある“指示待ち”を生む要因
パワハラ体験
強く叱られる、恥をかかされる経験があると、
もう目立たないようにしよう
波風立てずに仕事しよう
マイクロマネジメント
細かすぎる指示や過干渉は、考える力を奪います。
どうせ自分でやっても修正されるなら、最初から何もやらない方がいい
と学習してしまうのです。
成果が認められない風土
頑張っても評価されない、感謝されない。そんな環境では、
どうせやっても意味がない
と無力感が定着していきます。
なぜ指示待ち社員が増えたのか?社会背景から考える
教育の変化
昭和時代の集団主義・空気を読む文化から、平成以降は「個性を大切に」という方向へシフト。
さらに、受験教育では「正解のある問題」に答える力ばかりが求められ、自分で仮説を立てて動く訓練はほとんどされてきませんでした。
社会・経済環境の変化
以下のような社会的背景も、指示待ち傾向を助長しています:
- 頑張っても報われない社会
- 終身雇用の崩壊
- 成果主義と自己責任論の浸透
- タイパ重視で“余計なこと”をしない志向
こうした流れの中で「言われたことだけやるのが一番無難」という考え方が主流になってきた側面もあります。
上司の接し方が「指示待ち」を助長していることも
マイクロマネジメント
一挙手一投足に口を出しすぎると、
考えるな、言われたことだけやれ!
というメッセージになってしまいます。
自分でやってしまう
自分でやったほうが早いから。。。
と部下に任せず、自ら仕事を抱えてしまうことで、部下は“任される経験”を積めなくなります。
フィードバック不足
ここが良かったね!でもこれはこう改善できるかも!
などのフィードバックがないと、何が良くて何が悪かったのかもわからないまま、不安だけが残ります。
指示待ち社員を変えるために上司ができること
1. 信頼関係の構築
まずは安心して話せる関係性を築くことが最優先。 1on1や雑談の機会を増やし、「この人には相談しても大丈夫」と思える土台をつくりましょう。
2. ミスを責めず、成長のきっかけに
「なぜ間違えたんだ!」ではなく、「次はどうすればうまくいくと思う?」と建設的な会話を。 上司自身が失敗談をオープンにするのも効果的です。
3. 成功体験を意識的に与える
小さな仕事でも「これは自分で考えてできた」という実感を持たせると、自信が育ちます。
人事・組織ができるアプローチ
キャリアプランの明確化
「あなたがこの会社でどう成長できるか」を本人と一緒に描いていくことが大切です。
目標を持てば、自律的な行動の種になります。
評価制度の見直し
プロセスや挑戦そのものを評価できる仕組みにアップデートを。
結果だけで評価すると、安全策しか取らない社員が増えます。
外部研修の活用
社外の講師やプログラムを使うことで、「社内では伝えにくいこと」がストンと伝わることもあります。
特に若手には、第三者の言葉が響く傾向も。
チーム全体で変えていくという視点も忘れずに
- 週1のチームMTGで困りごとや工夫を共有する
- ペアワークや相互レビューの仕組みを導入
- 「あの人に聞けば大丈夫」という関係性をつくる
個人の問題にせず、「チームの文化」として“自ら動く”を育てていくことが大切です。
動画研修も効果的に活用できる
動画研修のメリットは以下のとおりです:
- 上司ごとの教え方のブレをなくす:誰が教えても同じ品質で伝えられる
- わからないときにすぐ見返せる:自分のペースで復習が可能
- 自分のタイミングで学べる:隙間時間での視聴が可能になり、主体性を刺激する
動画は“受け身な研修”ではなく、“自律学習を促すツール”として設計することで、指示待ち思考の改善にもつながります。
まとめ:指示待ちは“可能性の種”
指示待ち社員を「やる気がない」と切り捨てるのは簡単ですが、その多くは“育て方”や“職場環境”によって生まれたものです。
本人の中にある不安や過去の経験、そして今の組織の制度や上司の対応。
そのすべてを少しずつ変えていくことで、驚くほど変化が生まれることもあります。
大切なのは「性格の問題」ではなく、「関わり方と環境」だという視点です!
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました!
映像制作テンツキでは、
- クライアント用説明動画
- 新人社員マニュアルの動画化
- 研修動画の構成・企画・制作
などを行っています。
アニメで「視覚的にわかる」
ストーリーで「理解が深まる」
ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、
お気軽にご相談ください!