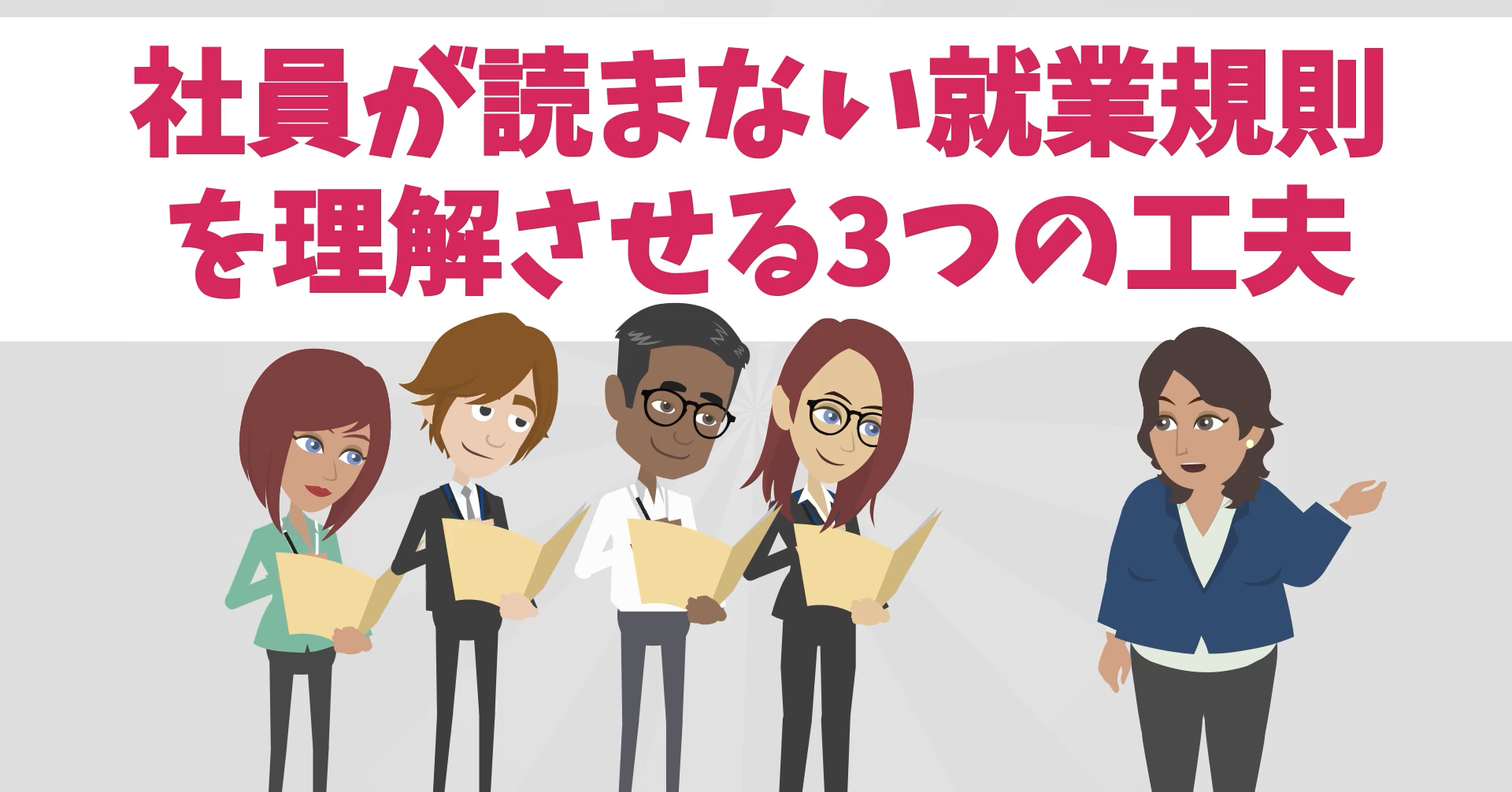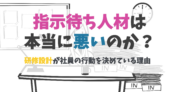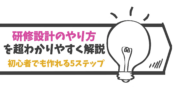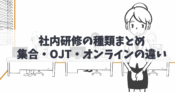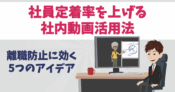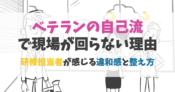社員が読まない就業規則を理解させる3つの工夫
結論:就業規則は「渡すだけ」では機能しない

就業規則を作って社員に配布し、署名をもらった時点で「義務は果たした」と安心している企業は少なくありません。
しかし実際には、配布だけでは社員に内容が伝わらず、労務トラブルの火種を残してしまうのです。
就業規則は会社と社員を守るためのルールブック。存在を形だけ整えても、使えなければ意味がありません。
では、どうすれば「社員が本当に理解している状態」に近づけるのでしょうか?
この記事では、その工夫を具体的に解説します。
就業規則は“渡すだけ”ではダメ。理解されて初めて、会社を守る力を発揮します!
なぜ「配るだけ」では危険なのか
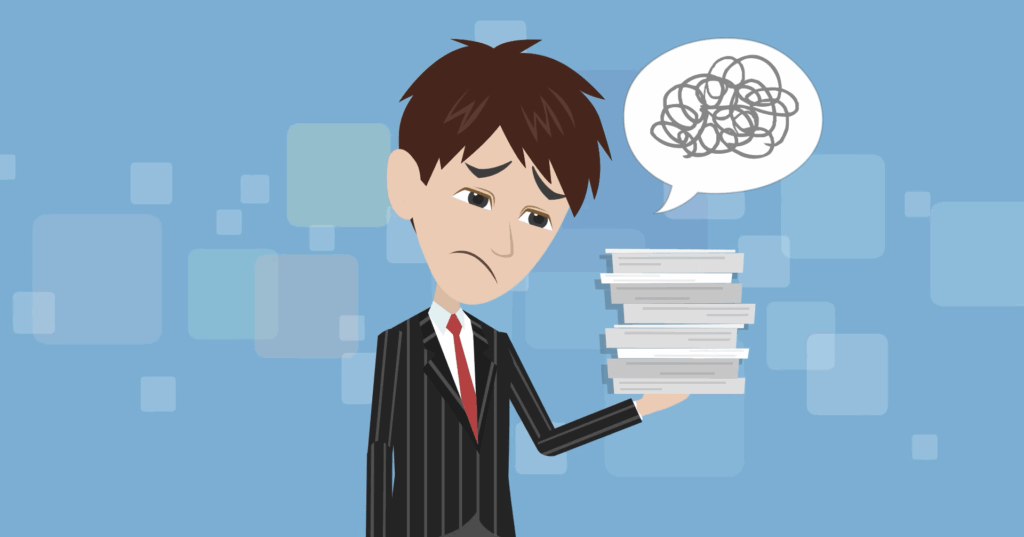
理由①:社員が内容を読まない
正直なところ、就業規則を最初から最後までしっかり読む社員は、ほとんどいません。
分厚い冊子のような就業規則は、ページ数も多く専門用語も多いため、読むだけで疲れてしまうのが現実です。
とりあえず署名だけして提出しておけばいいんでしょ?
そんな感覚で受け止める社員が多いのも無理はありません。
でも、この“読まれない”状態こそが大きなリスク。
肝心なルールが社員の頭に入っていなければ、当然ながらトラブル時に「そんなこと聞いていない」と反発される可能性が高まります。
理由②:「知らなかった」がトラブルに発展
就業規則を理解していないと、日常の働き方の中で小さなすれ違いが積み重なります。
たとえば──
- 残業の命令があったとき、「そんなルールあるなんて知らなかった」と拒否される
- 有給休暇の取得条件を誤解して「勝手に休んだ」と扱われる
- 懲戒処分の対象になる行為を知らずに繰り返してしまう
こうした“知らなかった”によるトラブルは、社員にとっても会社にとっても大きなストレスです。
一度こじれてしまうと、労務問題に発展したり、不信感から退職につながったりするケースもあります。
つまり、理解不足は単なる知識の問題ではなく、信頼関係そのものを揺るがす危険性を持っているのです。
理由③:周知義務を果たしたつもりでも不十分
会社としては「配布して署名を集めたから大丈夫」と思いがちですが、実はそれだけでは不十分です。
労働基準法では「就業規則を社員に周知する義務」がありますが、形式的な配布や掲示だけでは“実態として理解されていない”と判断されることがあります。
特に裁判などの場面では
- 「社員が実際に内容を把握できていたか」
- 「説明の機会を設けていたか」
- 「理解できる形で伝えていたか」
といった点が重視されます。
つまり、ただ渡して署名を集めただけでは、いざというときに会社を守れない可能性があるのです。
就業規則を“配って終わり”にすると、読まれない・理解されない・会社を守れない。三重のリスクが潜んでいます!
就業規則は「理解されて初めて意味がある」
就業規則は“読まれるため”ではなく、“使われるため”にあるのです。
就業規則の目的は、社員に一度目を通してもらうことではありません。
本当の意味での役割は、日々の業務やトラブルの場面で“使える知識”として活かされることにあります。
例えば──
- 休暇ルールを理解していれば現場が混乱しない
「誰がいつ休めるのか」「代替要員はどうするのか」が明確になれば、突然の欠勤やシフトの穴埋めでバタバタすることが減ります。 - ハラスメント規定を理解していればリスクを下げられる
「これはアウト」「ここまでならセーフ」という共通認識があることで、職場の安心感が高まり、不必要なトラブルを未然に防げます。 - 懲戒基準を理解していれば会社を守れる
トラブルが起きたときに、規則を根拠に処分できれば「感情的な判断だ」と疑われることなく、会社の正当性を主張できます。
さらに言えば、就業規則が“使えるルール”になっていると、社員側にとってもメリットがあります。
- 「休暇が取りやすい会社なんだ」
- 「処分の基準が明確だから安心して働ける」
そんな安心感が信頼につながり、定着率の向上にも寄与するのです。
就業規則は読むだけの紙ではなく、社員と会社を日常的に守る“実用ツール”。理解されてこそ意味があります!
社員が理解するための4つの工夫
では、どうすれば「配布して終わり」から脱却できるのでしょうか。
工夫①:ポイントをまとめた資料を作る
- 有給休暇
「何日前に申請すればいいのか?」「繁忙期でも取れるのか?」など、現場で必ず出る疑問をまとめると安心感につながります。 - 残業・休日出勤
「どのような場合に命じられるのか」「割増賃金はいくらになるのか」など、誤解が多い項目です。 - 副業
解禁する企業が増えている今、ルールを曖昧にするとトラブルの原因になりやすいので、明文化して伝えることが大切です。 - ハラスメント防止
「どんな行為がアウトなのか」を具体例付きで示すと、社員もイメージしやすく予防効果が高まります。 - 懲戒処分
「遅刻や無断欠勤を繰り返すとどうなるのか」「会社の備品を勝手に使ったら?」といったケースをQ&Aにすると、抑止力としても機能します。
これらをただ文字で列挙するのではなく、Q&A形式やチェックリスト形式にまとめるのがおすすめです。
「自分に関係あることだけを素早く確認できる」形にすることで、社員の理解度は一気に高まります。
「“全部読む”はムリ。だからこそ“要点資料”で理解しやすくするのが効果的!」
工夫②:説明会や研修をセットにする
就業規則を配るだけでは社員は読みません。そこで効果的なのが、説明会や研修の場を設けて口頭で伝えることです。
人は文章を読むより、直接説明を受けたほうが記憶に残りやすいもの。
特に入社時や規程改定時に、就業規則のポイントを人事や専門家から説明してもらうと、社員の理解度が一気に高まります。
さらに効果的なのは、小テストやクイズ形式で確認することです。
例:
- 「残業を命じられるのはどんな場合?」
- 「パワハラに当たる行為を3つ挙げてください」
- 「有給休暇は最短で何日前に申請すべき?」
こうした問題を出すと、社員は受け身ではなく“考えながら学ぶ”状態になるため、理解度も記憶定着率も上がります。
説明会+理解度チェックで、“配布だけ”から“周知できている状態”に進化します!
工夫③:動画や図解で伝える
文字だけの分厚い就業規則を社員に読ませるのは、ほぼ不可能に近いですよね。
そこで役立つのが、動画や図解といった“ビジュアルで伝える工夫です。
例えば──
- 3分程度の短い動画に要点をまとめて、いつでもスマホから見られるようにする
- 漫画やイラストを活用し、NG行為やルールを直感的に理解できるようにする
- スライド事例を見せながら「この行動はセーフ?アウト?」と考えさせる
こうした形式なら、社員は自分のペースで何度も復習できます。
特に動画は「繰り返し同じ質で伝えられる」ため、上司ごとの説明のバラつきも防げます。
動画や図解は、理解を“わかりやすく・何度でも”サポートしてくれる最強の味方です!
工夫④:定期的なフォローをする
就業規則の説明は“一度やったから終わり”ではありません。
法律改正や会社の状況変化に合わせて、規程は更新されるもの。だからこそ定期的にフォローする仕組みが必要です。
例えば──
- 人事評価面談や1on1の場で「就業規則に関して不明点はある?」と聞いてみる
- 社内チャットに「よくある質問コーナー」を作り、誰でも気軽に確認できる環境を整える
- 掲示板や社内報で「最近の注意点」や「法改正のポイント」をシェアする
こうした取り組みを継続すると、就業規則が「棚に眠る存在」ではなく、日常的に使われるルールに変わります。
就業規則は一度説明したら終わりじゃない。定期的に思い出してもらうことで“生きたルール”になります!
社労士としてできるサポート
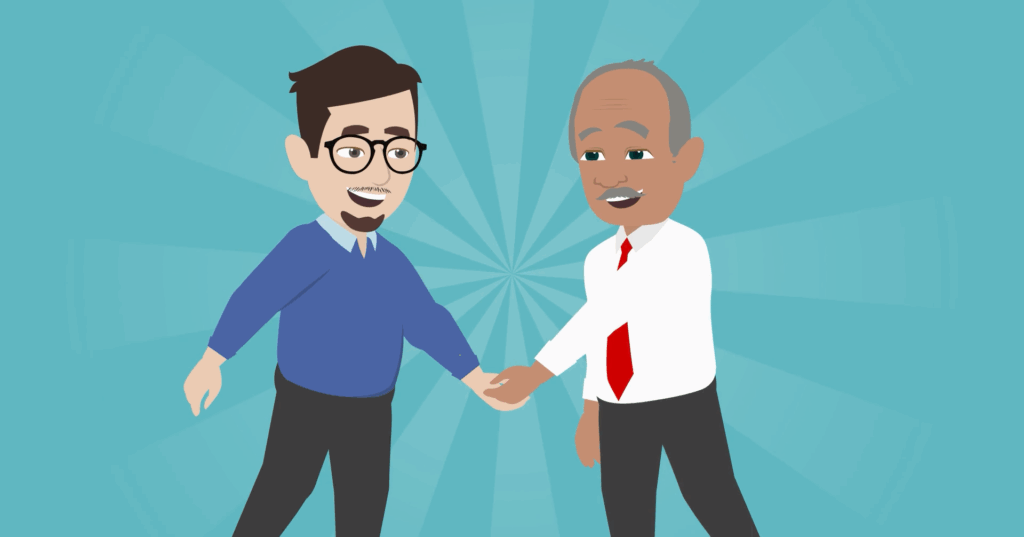
「就業規則を作ること」──多くの企業が社労士に依頼するのはこの部分です。
しかし、社労士が本当に力を発揮できるのは、規程を作った“その先にあります。
例えば、こんなサポートが可能です。
- 顧問先に「配布だけでは危険」と伝える
就業規則は作成して終わりではなく、社員に理解されなければ意味がないことを、経営者や人事担当者にしっかり伝える。 - 周知の仕組みを提案する
説明会の実施方法や、わかりやすいQ&A資料の作り方など、実務に落とし込みやすい方法を一緒に考える。 - 動画や教育ツールを提供する
文章だけでは伝わりにくいポイントを、動画や図解などで「いつでも学べる形」に変換。これにより、現場の説明負担を減らしつつ理解を深められる。 - 改定に合わせた“社員説明の場”を設計する
法改正や社内ルール変更に合わせて「どう伝えるか」をセットで提案する。これによって、規程が常に最新の状態で浸透し続ける。
こうした支援があると、企業側は「就業規則が実際に機能している」安心感を持てますし、社労士としても「トラブルを未然に防ぐ専門家」として信頼を得られます。
単なる規程作成の専門家ではなく、ルールを企業文化として根づかせるパートナーとして立ち位置を確立できるのです。
社労士の強みは“作る”だけじゃない。“伝えて浸透させる仕組み”まで支援できることです!
まとめ 〜就業規則は“理解されてこそ”意味がある
就業規則は、会社と社員の関係を守る大切なルールブックです。
しかし、配布して署名をもらっただけでは本当の役割を果たせません。
「知らなかった」「聞いていない」という一言で、残業、有給、ハラスメント、懲戒といった労務トラブルは一気に広がります。
だからこそ、就業規則は**“形だけ”ではなく“理解されている状態”**にしなければならないのです。
そのために有効なのは──
- 要点だけを抜き出した資料化
- 入社時や改定時に行う説明会・研修
- 何度でも学べる動画化や図解
- 継続的に理解を深める定期フォロー
これらの仕組みを整えることで、就業規則は「机の奥に眠る書類」から「日常的に役立つ実用ツール」に変わります。
そして、その設計を支援できるのが社労士の大きな強みです。
就業規則は“形だけ”では会社を守れない。社員に理解されてこそ、真の武器になるのです!
おまけ:アニメーション研修動画や動画マニュアル作成に興味ある方へ
などを行っています。
- アニメで「視覚的にわかる」
- ストーリーで「理解が深まる」
- ナレーションで「補完できる」
この3つを活かすことで、
専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。
という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。
顧問先対応をもっと効率化したいと感じているなら、“動画で仕組み化”する第一歩を踏み出してみませんか?